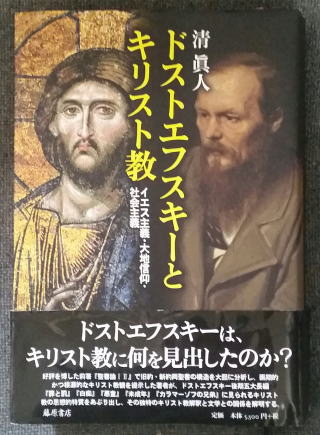
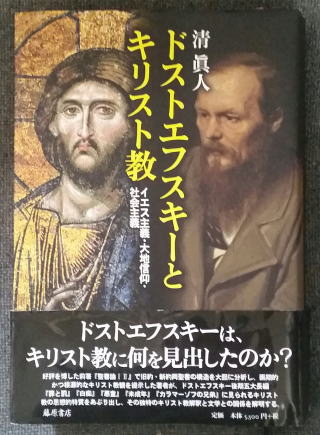
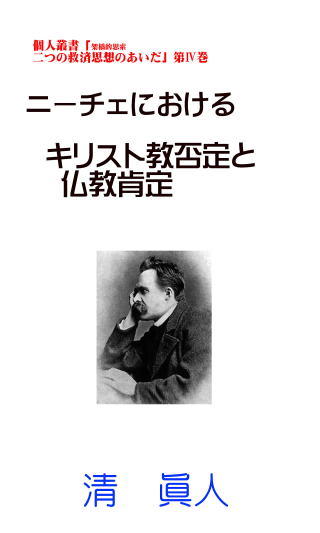
第五章 ルサンチマンをめぐって
――ニーチェとヴェーバー
序章「眺望 一九三三年」(清による全訳)
第Ⅰ章「子供時代」(清による抄訳)
第Ⅳ章「前線」からの抜粋(清による抄訳)
第Ⅹ章「革命」からの抜粋(船戸満之訳を土台に)
第Ⅺ章「バイエルン
最終章「五年間」からの抜粋(同前)

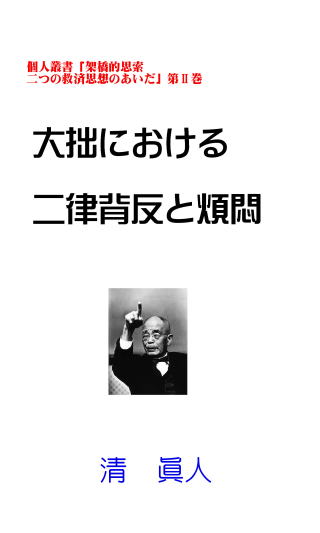
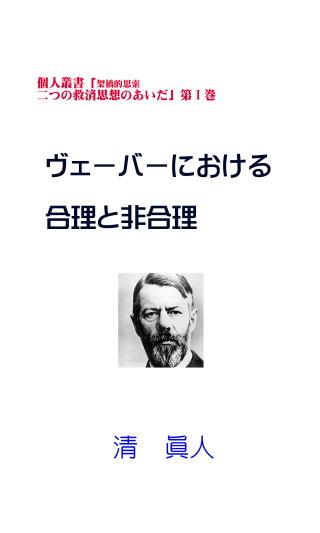
第一章 「大拙大乗経」における宇宙原理――「華厳法界(事事無礙)」
はじめに――私のヴェーバー理解の転回
第Ⅰ部 ヴェーバーにおける合理と非合理、
その複層的交差性
ドストエフスキー文学という鏡
イエス的愛とヤハウェ主義的道徳主義との対立
ヴェーバーの内的葛藤についての妻マリアンネの指摘
「
補注2 「アコスミッシュ akosmisch」という形容句について
第Ⅲ部 「市民」的合理性をめぐる問題の布置図
アジア社会との関係
補注3 丸山眞男の『忠誠と反逆』について
ロシア社会との関係
後期資本主義との関係
付論
二つの救済欲求の両極性と対話可能性について
――叢書「架橋的思索 二つの救済思想のあいだ」に寄せて
一 私の問題設定
補注1 一つの事例、大乗仏教における「救世主」要素についてのヴェーバーの考察
補注2 『リグ・ヴェーダ』に見られる創造主的人格神と汎神論的非人格的宇宙神の混淆性
二 ニーチェについて
三 汎神論的宇宙神と憐れあいの神とは如何に媒介可能か?――「マタイ福音書」に寄せて
補注3 大乗仏教とグノーシス派の近似性についての
湯浅奏雄の指摘
結び
付記 本書の出版と同時並行して。私はAmazonkindle電子書籍セルフ出版による個人叢書「架橋的思索 二つの救済思想のあいだ」を刊行した。
第Ⅰ巻『ヴェーバーにおける合理と非合理』、
第Ⅱ巻『大拙における二律背反と煩悶』、
第Ⅲ巻『二人の葛藤者――ヴェーバーとトラー』、
第Ⅳ巻『ニーチェにおけるキリスト教否定と仏教肯定』である。
なお今後、第ⅴ巻『田辺元における「第二次宗教改革」構想』、
第Ⅵ巻『鏡としてのドストエフスキー』、
第Ⅶ巻『西田幾多郎と三木清』を予定している。
あとがき
想えば、私が自分の著書にフロムを、しかも大きな照明をあてて登場させたのは二五年前にさかのぼる。一九九三年に私は学生男女を読者に想定して『空想哲学スクール(一九九三年汐文社)という書名の本を二冊目の単著として出版したが、この本は二部構成となっており、その三分の二を占める第二部「愛について――フロムを読む」はタイトルにあるように、かの『愛するということ』に盛られたフロムの考察を、まさに「愛」についての考えを深めるための貴重で有効な問題提起として学生たちに紹介する試みであった。私は、フロムの議論を学術的に論評するのではなく、何よりも学生たち自身の愛にかかわる様々な経験に直にかかわらせ、あるいは評判をとった映画や歌にもかかわらせ、いわばそれらを挟んでフロムと彼らとのあいだに対話が始まり、それを通じてそこに孕まれている問題がいっそう彼ら自身の《問題》としてくっきり浮かび上がってくるように論述を工夫した。この第二部は十八章・二三〇頁の分量のものとなった。
それから四半世紀たって、こうして私はまたフロムについてかなり大部な本書を、今度は専門の学術図書として出版することとなったわけである。本書においても彼の「生産的愛」の思想は重要な考察対象となっているが、書名にあるとおり、本書の特徴は、宗教文化の分野のなかで「神秘主義」と呼び慣わされてきた伝統から彼が何を如何に摂取したのかという問題に焦点をあて、かかる問題の環を梃に彼の思索的営為の全体像を浮かび上がらせ、その問題構造に照明を与えようとした点にある。かくて、おのずと本書はフロムの宗教論に多大な関心を寄せるものとなった。これまで、日本におけるフロムへの注目は、多くの場合、彼における精神分析学と社会学との接合の試みが現代人の抱える心理的諸問題の解明に如何に貢献してきたかという側面に集中してきたと思われる。だが本書は、その問題側面もさることながら、彼の思索的営為の最も奥深いバックグラウンドをなすものとして彼の「神秘主義」論を取り上げ、またそれに陸続する彼の宗教論の諸局面に光を与えるべく努めたのだ。
ところで、かかる作業に取り組んでいるうちに私はあらためて深い感慨に襲われずにはおれなかった。彼の思索者としての全体像を《我がものとする》ために辿る私の調査追跡の一歩一歩の行程は、思考者としての私自身がこの三十年近く歩いてきた「異種交配化合」の一歩一歩の行程を脳裏に復原せしめ、その自らの行程を彼の行程に突きあわせ、彼と渡りあう行程となったからである。
「異種交配化合」とは何か?
私は一貫して次の信念を持してきた。すなわち、思考の創造的展開は必ずや「異種交配化合」から生じるとの。
この信念は次の信念に掉さす。すなわち、思索はつねに思索者自身の或る痛切なる生の経験からのみ誕生することができる。そして、生の経験とはつねに多種多様な諸契機の総合からなる全体的なものであり、その全体性は、つねにその思索者のそれまでの思考の枠組みには収まり切れない暗き余剰の圧迫をもって彼・彼女を動揺させる。思考はつねに或る断面を切り取る作業として作動し、だから同時にまた自分が切り取ることなく、《我がものとすること》ができず、そこに放置したままにしているものの存在を片目でにらむ作業でもある。全体を尽くすことができない己の限界を、この経験の暗き余剰の圧迫の前に露呈することなしには、実は思考の作業は展開しないのだ。そして、この片目の担う自覚は、自分がまだ為しえないでいることに、既に自分に先駆けて――完全にやり遂げたかは別にして――着手している、己にとって「異種」なる別な思考がこの世に存在していることに気づくことでもある。
だから次に「異種交配化合」の局面が来るのだ。
生の経験が痛切であればあるほど、経験者は、それを《我がものとする》ためにその「異種」なる思考とこれまでの自己とのあらためての「異種交配化合」に進まねばならない。
精神分析者であるフロムにとって、フロイトとの邂逅が彼の知識人人生の進行方向を決定したことはいうまでもない。だが、彼がフロイトのたんなる追随者ではなく、鋭いフロイト批判を媒介にして、フロイトから受け継いだ精神分析学をさらに「人間主義的精神分析」へと創造的に発展させる者となるためには、彼は自分をこの新たなる創造に向かわせる契機を必要とした。その契機となったものは、フロイト的思考の外部にあって、しかし、フロム自身にとっては、それとの対話があらためて不可避なものとなったという意味で既に半ば内在化していた或る幾つかの――まさに私の言い方を用いれば――「異種」的契機である。
私は「異種交配化合」の視点に立ってこう言ってみたい。
まずここで「フロイト主義者としてのフロム」という軸を立てる。そのフロムにとって、「フロイト主義」だけでは切り取ること、《我がものとすること》ができぬ暗き余剰を抱えた或る痛切なるフロム自身の生の経験がやって来る。その経験は彼をくだんの「異種」の存在へと振り向かせる。彼は片目でこの「異種」をにらむ。実は彼にあってそれらは、まずフロイトに先んじてあるいは平行して、否応なくフロムを深く惹きつけたものであったがゆえに既に自身に内在化していた、「フロイト主義」に対する異種の契機であった。いまやそれらが改めての「異種交配化合」のテーマへと競り上がる。
それら諸契機とは、彼の証言によれば、彼が幼少期以来実は親しんできたユダヤ教神秘主義が生きる「メシア主義」であった。バッハオーフェンであった。禅仏教であった。『経済学・哲学手稿』の初期マルクスであった。フロムは、これらの諸思想と「フロイト主義」との「異種交配化合」として彼の「人間主義的精神分析」を生みだした。
では、この彼の「人間主義的精神分析」は彼のその生の経験を完全に《我がものとすること》を彼に可能にしたのか? おそらく否であろう。
私は、本書において彼の「神秘主義」理解と「空」理解の問題性を批判した。私の言葉で言えば、神秘主義的経験の孕む「法悦的瞑想」の契機=「浄化的カタルシス」の問題はフロムにとってはまさに未だ《我がものとすること》ができないものに留まっている、と。またこの視点からみれば、マルクーゼは後期フロムにとってとりあえずは拒絶の対象として、しかし、実は改めて「異種交配化合」が問題となる相手として問題化するのではないか、とも私は考えた。
いったい誰が、己の生の経験の全体性を思索的に完璧に《我がものとする》ことができると言うのか? あらゆるものは途上にあるほかない。問題は、途上にあるか、途上にすらないか、である。フロムは確実に途上に立つことができた。そう私は思う。
私は高校生になって「マルクス主義者」たらんとした。それが私の思索者としての人生の開始である。思索と生の経験とのくだんの確執は、まず覚えたての「マルクス主義」が私にもたらした「理論的思索」と「文学」との確執となって私の前に登場した。当時、そして今でも、私の「異種」とはつねにまず文学である。私の最初の「異種交配化合」の試みは、マルクス主義的思考と実存的思考との、そして実存的思考が内部に抱えている精神分析学的思考つまり実存的精神分析との「異種交配化合」の試みである。しかも、その時は「マルクス主義的思考」といっても、既にスターリン主義的マルクス主義を如何にのりこえ「マルクス主義」の創造的再生を果たすかという問題意識に立つ新マルクス主義であった。この自己の再生を期待する新マルクス主義の企ての中核にはまさに『経済学・哲学手稿』の初期マルクスが立っていた。そして当時の私にとって、最初の「異種」はサルトルであり、己を妄想のうちに閉じ込めることで辛くも生き延びようとする《想像的人間》をつねなる主題に据える彼の実存的精神分析学であり、サルトルとの格闘はそのうち私の眼をニーチェにも向けさせた。
この問題系列は私の次の著書の系列となって現れた。『〈受難した子供〉の眼差しとサルトル』(一九九六年、御茶の水書房)、『実存と暴力−−後期サルトル思想の復権』(二〇〇四年、御茶の水書房)、『《想像的人間》としてのニーチェ――実存分析的読解』(二〇〇五年、晃洋書房)、『三島由紀夫におけるニーチェ――サルトル実存的精神分析の視点から』(二〇〇九年、思潮社)、『サルトルの誕生――ニーチェの継承者にして対決者』(二〇一二年、藤原書店)、『大地と十字架――探偵Lのニーチェ調書』(二〇一三年、思潮社)。
フロムの「人間主義的精神分析学」は彼自身が強調するように「実存的二分性」を人間の実存の本質規定とする観点から出発し、またこの観点は彼の宗教論を導く根幹的視点でもある。そして「人生の意味」の授与者の位置に創造主神を置く正統キリスト教の視点を拒絶し、宇宙との豊饒なる応答性が生む諸個人における生命感に満ちた自己発現・自己実現の「悦び」のうちに人生を意味づける「自己目的」的価値性を見ようとするフロムの視点は、ニーチェとの共感と反発に引き裂かれたアンビヴァレントな関係を秘めている。
この彼の思索の根幹に前述の私の著作系列は著しく反応せざるを得なかった。
私の第二の著作の系列は、『空想哲学スクール』以来、一貫して《経験と思索との往還性》をテーマに学生たちと対話することにあった。続いて、『ヴィジョンは〈世界〉をつれて――生きるアートの哲学』(一九九七年、はるか書房)、『経験の危機を生きる――応答の絆の再生へ』(一九九九年、青木書店)、『いのちを生きる いのちと遊ぶ――the philosophy of life』(二〇〇七年、はるか書房)、『創造の生へ――小さいけれど別な空間を創る』(二〇〇七年、はるか書房)が書き綴られた。 これらの書名が、またそのサブタイトルが示唆するように、これらの著作にはフロムのかの「応答責任」と「応答関係能力」の視点、また「市場的構え」を打ち破り如何に「生産的性格」を己に取り戻すかというテーマ、「持つ」のではなく「在る」が如何に真の自己発現をもたらすかというテーマ、これらが学生たちへの恰好の問題提起として紹介されている。同様にまたブーバーの「私‐君」関係性の思想や「現実は共有されてこそ現実へと競り上がる」という視点も。
そして、私はこの二つの問題系列を追究しているうちに、あらためて宗教の問題を本格的に考えたくなった。打ち明けていえば、二十世紀におけるマルクス主義革命運動の悲劇的かつ根底的な挫折、自己崩壊という問題は、私に「革命」(マルクーゼの概念を使えば、「全体的で根底的な質的革命」としての)の不可能性という問題を突きつけると同時に、それこそ、本書で注目したフロムの言う「あらゆる理想主義的文化が抱えるところの《宗教性》」という問題に私を送り返した。「ユートピアから科学へ」あるいは「宗教から科学へ」は私のなかで「科学からユートピアへ」あるいは「科学から宗教へ」にひっくり返され、「ユートピア」あるいは「宗教」(不可能性)と「科学」(可能性)のあいだに引き裂かれ宙吊りにされている現代のわれわれの姿が私の意識の真正面に競り上がった。
フロムの言う「無神論的宗教性」の視点が身に染みた。
驚愕的な科学技術の発展と、まさにそれに反比例するような人間性の不変性あるいは劣化、この二者の驚くべき不均衡が生む現代史の跛行的展開、それは確実に人類史の終焉を歴史の射程の内に収めたと思われる。
私は否応なく人間の文化の根源をなす宗教の問題に還らざるを得なかった。
完全なるアマチュア作業だが、といっても、私にとって書くことはつねにそれだが、宗教論に手を染めた。第三の系列が生まれた。
それははまず二〇一五年の『聖書論Ⅰ 妬みの神と憐れみの神』と『聖書論Ⅱ 聖書批判史考』(藤原書店)となって現れた。そこでの宗教論探究の試みのいわば参照軸となったのはヴェーバーの『古代ユダヤ教』であり、『ヒンドゥー教と仏教』であった(最近、これに『宗教社会学』が付け加わった)。と同時に、私は『聖書論Ⅰ』にこう書き入れていた。「私には一つの試みてみたい視点があった。その視点とは、バッハオーフェンに始まり、日本では『文化圏的歴史観』を提唱した石田英一郎がそのもっとも有能な継承者であると思える一つの視点、一言でいえば、人類の宗教・文化史の軌跡を《母権的価値体系と父権的価値体系との相克》――それは当然混淆化という問題を伴う――というコンテクストを基軸に考察するという観点である」と。
二〇一六年に『ドストエフスキーとキリスト教――イエス主義・大地信仰・社会主義』(藤原書店)を書いた。高校生のときドストエフスキーに出会ってから、いつしか私の夢の一つとなっていたのだ、ドストエフスキーについて書くことが。「マルクス主義者」たらんとした高校生の私の片目はつねに彼に注がれていたからだ。その夢を果たした。そこには、「マルクス主義」の破産を総括するための一つの予言的意義をもつ苦闘を彼のなかに跡付けたいという想いも差しはさまっていた。サブタイトルはそのことを示唆している。そしてこのあと、私はほとんど新書一冊の分量の紀要論文「一つの対話をもたらす試み――ヴェーバー・ドストエフスキー・大拙」(二〇一七年)と「二人の葛藤者――ヴェーバーとトラー」(二〇一八年)を、この問題系列の継承として書いた。前者において、私は鈴木大拙に踏み込んだ。後者では、ヴェーバー自身が実は相反する二つの精神の葛藤、父的なプロテスタント的合理主義と母的な「
「わたしはもはや〈新しい〉人類への変容を信じない。…〔略〕…わたしは〈人間はあるがままのものになる〉という悲劇的かつ慈悲深い言葉の意味を今までよりずっと深く感じている」。
いわば、私はこの三十年間の私における「異種交配化合」実験の総力を挙げてフロムを論じたのだ。
最後となるが、この私の最近の実験の数々を快く出版してくださった藤原書店の藤原良雄社長と、そのさいつねに編集を担当してくださった小枝冬美氏に心よりの感謝を捧げたい。
二〇一八年初夏に記す
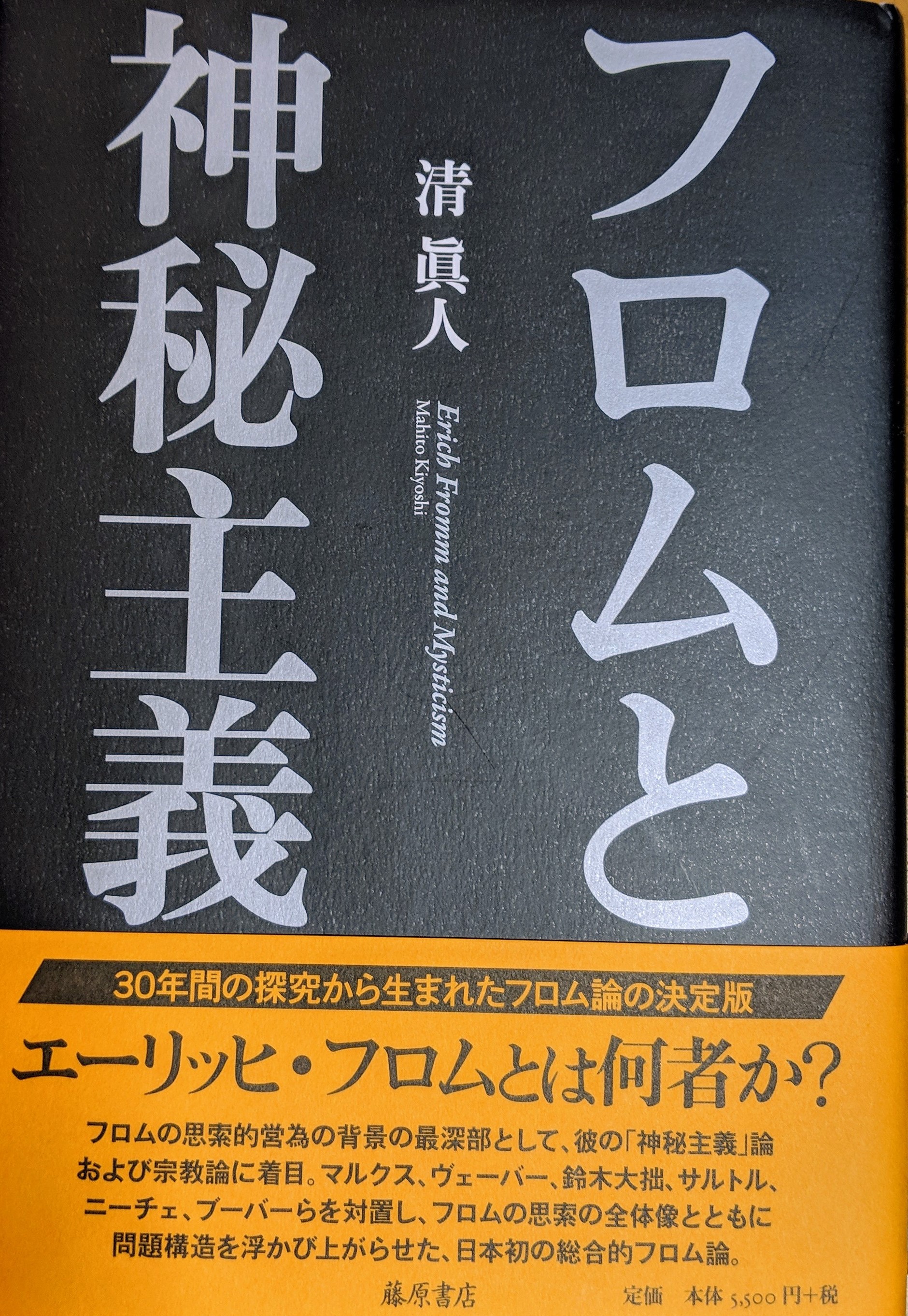
第三章 「少女凌辱」というテーマの問題位置
第四章 汎神論的大地信仰とドストエフスキー、そしてニーチェ
第五章「カラマーゾフ的天性」とは何か? ――悪魔と天使、その分身の力学
『二重人格』の異様さ
『地下室の手記』第一部に提示される「意識=病」論をめぐって
『地下室の手記』の二部構成に潜められているもの
蟻塚・水晶宮・暴力・正義・活動家
あとがき
私が本書で追究する主題は、ドストエフスキーがこれこそが真のキリスト教だとみなすそれ、つまりドストエフスキー的キリスト教の思想的特質を、彼の後期五大長編世界――『罪と罰』、『白痴』、『悪霊』、『未成年』、そして最後の作品『カラマーゾフの兄弟』――と、それに平行して書き綴られた彼の評論集成『作家の日記』を渉猟することであぶりだし、あらためて彼の独特なるキリスト教解釈と彼の文学との深甚なる関係を解明することである。
ここであらかじめ一言するならば、彼がキリスト教の真髄をどの点に見いだしたのかという問いと、彼が如何なる人間認識・人間観の持ち主であったかという問いとは表裏一体の切り離しがたい関係を形づくっている。
私は本書において、彼の五大長編と『作家の日記』はもとより、それ以外の論及欠くべからざる諸作品も取り上げながら、彼特有の人間認識の諸側面をできる限り鮮明に浮き彫りにしようと努めた。たとえば本書第五章「『カラマーゾフ的天性』とは何か? ――悪魔と天使、その分身の力学」では、まず『カラマーゾフの兄弟』のなかで父親殺しの嫌疑をかけられた長男ドミトリーの裁判において検事補イッポリートが口にする「広大なカラマーゾフ的天性」という言葉を取り上げ、それをこの検事補が次のように定義していることに注目した。すなわち、「ありとあらゆる矛盾を併呑して、頭上にひろがる高邁な理想の深淵と、眼下にひらけるきわめて低劣な悪臭ふんぷんたる堕落の深淵とを、両方いっぺんに見詰めることができる」性格ないし力と[1]。
かつ次の事情に論及した。ドストエフスキー文学において、この「カラマーゾフ的天性」なるものが――それを広義に解釈すれば――たんにカラマーゾフ家の兄弟たちだけではなく、たとえば『悪霊』のワルワーラ夫人の性格でもあり、息子のスタヴローギンに継がれたそれでもある事情に。
彼女はそれを「飽くことを知らない
と呼ぶ[2]。またスタヴローギンは自殺にさいしておのれを振り返り遺書にこうしたためる。「いや、以前も常にそうだったのだが、善をなしたいという欲望をいだくことができ、そのことに満足を覚える。と並んで悪をなしたいという欲望もいだき、そのことにも満足感をおぼえる」(傍点、ドストエフスキー)と[3]。また、実にほとんど同じ言葉で『未成年』の主人公ドルゴルーキーはこの矛盾的渇望を彼自身の「謎」と呼ぶのだ[4]。同小説は『カラマーゾフの兄弟』の直前に位置する作品であるが、彼の自己省察の記録としての体裁をとるがゆえに、この「謎」をこれ全編にわたってあたかも『カラマーゾフの兄弟』への予行演習をなすが如くくりひろげることとなる。
そして私は次のように推測した。それはおそらくは作者ドストエフスキー自身の「天性」であり、彼はそれを自らの小説の主たる登場人物たちにくりかえし投影せざるを得なかったにちがいない、と。
その詳細はまさに第五章に譲るが、人間の本質をなすものとしてこの「反対極への渇望」を見いだす視点は(それは、ロシヤの民衆こそはこの本質を最も熱く凝縮的に生きるという特質をもつという、彼のロシヤ人観と深く結びついているのだが)、さらにまた「現代人」の、とりわけ屈辱の人生を強いられた個人史を抱え、深く怨恨的性格をもつに至った人物たちの魂の奥底に《「自虐の快楽」主義者と「自尊心の病」患者との双子の振り子機制》とでも呼ぶべき心理機制を突き止め、この機制の内に自らを幽閉してしまった魂の苦悶こそを「現代人」のなかのこのタイプの特有なる苦悩として把握する視点、それを彼に与えるのである。
というのも、彼は実に一貫してこの怨恨人型の人物の苦悶こそを彼の文学の何よりの追求対象に据えたのだが、彼らは実はドストエフスキー自身を含むところの当時のロシヤ・インテリゲンチャのなかから汲み取られた人物たちであり、彼らの自我とは西欧文化の摂取によって研ぎ澄まされた過剰なる自己意識をもっておのれのロシヤ的身体性に向き合わざるを得ないところに生まれる自己分裂、これによって特徴づけられる自我であった。そして彼らは自らの怨恨的性格によってこの分裂気質をいっそう過剰化せざるを得ない人間たちであった。なお一点注記すれば、この心理機制が性愛に投影されるや、彼らはその愛の経験においておのれの性欲が所有と侵犯の快楽を色濃く帯電したそれになっていることを見いださざるを得ず、愛の経験の他方の契機たる共苦の愛との鋭い対立に自ら陥り、愛の感情においても鋭い自己矛盾を経験するのだ。《作家》たるドストエフスキーのリアリズムはこの問題をけっして見逃しはしなかった。否、それどころかこの性の苦悶は彼の主題そのものであった。
では、ドストエフスキー的キリスト教はこの人間認識とどうかかわるのか?
まさにそれは、右の苦悶を裂開し、前述の心理機制の内におのれを幽閉する彼らの病める魂をそこから解き放ち、他者との嘘偽りのない素朴な正直な親しい交わりを取り戻させ、そこへといざない、その親交こそが初めて生みまた再生させる素朴な生命の喜びを、それだけが彼らの苦悶を癒す力をもつのだと確信し、この治癒力の贈与こそが魂の「医者」あるいは「看護師」として彼らにかかわらんとする者の仕事なのだと理解する思想、その源泉となるのだ。
彼らがどのような特有なる苦悶の仕方・心理機制を負わされているのかという前述の問題認識・対象認識は、当然、裏表の関係で、彼らには如何なる治療がほどこされるべきかという点を治療者はどのように自覚すべきか、という治療者の側の主体的認識・自己認識の問題へと反転しよう。ドストエフスキー的キリスト教こそはまさにこの治療者の主体的自覚の根幹に据えられるべき思想として問われるものとなる。
ドストエフスキーは新約聖書が描きだすイエスの人格、すなわち、自分の犯した罪に苦しむ人間に対して彼が取る態度に表出するその人格性と、それを凝縮した「憐みの愛」の思想・共苦の思想こそを、何よりもキリスト教の真髄とみなす。実にそれは、そもそも人間という存在が、その根本的な《弱さ》(実存的脆弱性)ゆえに抱え込まざるを得なくなる苦悶についての深い洞察といたわりに溢れたものであったのだ。
ここで、私は拙著『聖書論Ⅰ 妬みの神と憐れみの神』(藤原書店)の第Ⅱ部「イエス考」のなかの補注「《人間の根源的弱さへの憐れみの愛》の思想とドストエフスキー」の一部を引用したい[5]。というのも、本書『ドストエフスキーとキリスト教』はまさにそこに記した私の彼に対する視点、それをさらに徹底的に追求したいという動機から誕生したからである。
『マタイ福音書』にもっとも力強く表現される思想、人間はおのれの力(自力)では如何ともしがたい根源的な弱さが生む精神の病に冒された「病者」であり、神とはかかる「病者」としての人類へ慈悲と赦しの愛を与える「医者」であるという思想、だからまた、「義人」ではなく、くだんの「罪人」・道徳的弱者こそが身をもってこの慈悲愛のありがたさを理解するという視点、それを文学的に最も鮮烈に打ち出したものは――私の狭い読書範囲では――何といってもドストエフスキーの『罪と罰』におけるマルメラードフの言葉と形象であろう。
『罪と罰』の天才的構成において、なんと第一部第二章でラスコーリニコフの前に早くも登場する酔いどれマルメラードフは、この小説の根源的テーマが右のイエス思想にこそ据えられていることを一身に体現する象徴的人物としてこう述べるのである。(彼は自分の人間的弱さ故に最愛の娘ソーニャを家族のための売春稼業に追いやり、あまつさえソーニャが家族のために稼いだ最初の金の全部を気違いじみた飲酒――その自責からの自己逃避が生み、しかしその自責を「自虐の快楽」に変えるところの――に使い果たしてしまう人間として描かれる。)「おれたちを哀れんでくださるのは、万人に哀れみをたれ、世の万人を理解してくださったあの方だけだ〔略〕『来るがよい!わたしはすでに一度おまえを赦した……一度赦した……いまは、おまえが多くを愛したことをめでて、おまえの多くの罪も赦されよう…。』そしてうちのソーニャを赦してくださる〔略〕すっかりみんなの番がすむと、われわれにもお声をかけてくださる〔略〕『おまえらは豚にもひとしい! けだものの貌と形を宿しておる。だが、おまえらも来るがよい!』」と。
この神の言葉に智者や賢者が何故かと疑義を呈するや、神はこう答えたと、ドストエフスキーは筆を続ける。「彼らのだれひとりとして、自らそれに値いすると思った者がないからじゃ」と。更に、この神の慈悲に触れて、豚にも劣る最弱の者たちが「おいおい泣く」とき、その瞬間にこそ「すっかり合点がいく……いや、みながわかってくれる〔略〕主よ、御国をきたらせたまえ!」と[6]。
ドストエフスキーは彼の理解するキリスト教の担うこの根幹の問題文脈を「キリストの法則」、「キリストの掟」、「キリストの真理」あるいはそれが指示する「人間の掟」・「人間の自然法則」と呼ぶ(参照、本書三七、四八頁)。本書では度々それを彼の「イエス主義」と形容した。本書第二章「ドストエフスキー的キリスト教の諸特徴」はまさにそのタイトルにあるとおりこの問題側面を考察した章にほかならない。私はこの第二章のなかでさらに考察を進め、ドストエフスキー的キリスト教の特異性を構成する要素として次の二点を取り出した。
その第一点は、この「イエス主義」が「受難した子供の眼差し」――私の表現を用いるなら――をもって問題を見渡すという
私がいう「受難した子供の眼差し」とは、まさにこの幼少期の帯びる聖性をその最も悲劇的なあり方においていわば逆照射する視点、その得るべき愛の記憶を剥奪された子供の苦痛と悲しみ、さらにいえばそこから生まれる人生への最深の根をもつルサンチマン、それを抱え込まされた七転八倒の苦悶、それらを凝縮して、そこから人間とその社会を凝視する視点のことなのである。
そしてわれわれはこういわねばならない。この「受難した子供の眼差し」の頂点こそ、男に凌辱され、その相手をさせられ、その時の自らの醜行を想起し恥の意識に打ちのめされ、その果てに深い自己罪悪視に陥り自殺に走る少女の眼差し、これであると。このテーマが後期ドストエフスキー文学に如何に一貫して貫かれることになるか、それを私は本書第三章「『少女凌辱』というテーマの問題位置」で詳論した。
この特質、その「イエス主義」の視座がつねに「受難した子供の眼差し」と縒り合されているというドストエフスキー的キリスト教の第一の特質、それは本書にあっては第二章と第三章を繋ぐ線上に浮き彫りにされる。
では、第二の特質とは何か? それは、くだんの「イエス主義」が、聖母マリア(=大地母神に等置された)信仰を媒介とすることで、「大地への接吻」をその象徴行為とするロシヤ民衆の汎神論的な「大地信仰」(しかもヘレニズム起源の「黄金時代の夢」表象とも重ね合わされた)と結合され、両者の融合あるいは混淆が試みられることである(いうまでもなく、「大地への接吻」という象徴行為は『罪と罰』においてソーニャがラスコーリニコフにそれを迫る場面を嚆矢とする)。そして、この事情は先に見た事情、ドストエフスキー的キリスト教が梃子となって、主要な登場人物たち、つまりくだんの怨恨人たちをかの《「自虐の快楽」主義者と「自尊心の病」患者との双子の振り子機制》から解放することで救済するというテーマと緊密に結びついている。
というのも、ドストエフスキーはこの解放の梃子を次のことのなかに見たからである。すなわち、「現代人」たるロシヤ・インテリゲンチャがロシヤ民衆との乖離(
この「イエス主義」と汎神論的「大地信仰」との結合・融合・混淆の企てにおいて、「憐みの愛」・共苦する愛による救済というきわめて人格神的な表象と、あらゆる事象を「全一性」の下に「総合」する直観の高みがもたらす汎神論的カタルシス――「全自然界が実感されて、思わず『しかり、そは正しい』と口をついて出てくる」・『永遠調和の訪れ』(『悪霊』)――の獲得という救済表象とが奇しくも一体化する。
私はこの両者の結合がドストエフスキーにあってはどのような論理によって媒介されたのかを問い、こう把握した。――ドストエフスキー的キリスト教とは次の救済展望の提出者にほかならない。すなわち、人間は「大地信仰」が生みだす《宇宙的自然と他者と自己のあいだを循環してやまない〈生命〉の有機的な汎神論的な統一性》と自分との再融合を追求し、最も深い意味での〈生命〉の再生(=新生)を果たすことによって《愛》の感情的力(=生命力としての愛)を最高度の発揮のレベルに引き上げるべく努め、そのことで万人各自が「聖人」となり「神の子」となることで最終的に「互いに愛し合うようになる」関係性をこの地上に横溢せしめ確立すべきである、かかる展望の提出である。本書第四章「汎神論的大地信仰とドストエフスキー、そしてニーチェ」はまさにこの問題の環を――グノーシス派キリスト教も引き合いに出しながら――究明する章にほかならない。つまりくだんの第二の特質とは、本書第二章と第四章とを結ぶ線上に浮かび上がるのだ。
ところで、こうした本書の担う問題構成を語る私の言葉を聞いてこられた読者の脳裏には一つの問いが兆すにちがいない。それでは、彼のキリスト教の孕む問題の究明においてそもそも第一章にはどのような位置づけが与えられているのか? と。
第一章のタイトルは見てのとおり「社会主義とドストエフスキー」である。
実は、これまで縷々述べてきた全問題はこの問題、すなわち十九世紀末の西欧を席巻しだす社会主義思想に対して彼が如何なる態度を取り、どのような関係を結んだのかという、この第一章のテーマに流れ込むのだ。実はこの意味で第一章は扇の要の位置に立つのである。
くりかえせば、私はこう問題を立てた。《ドストエフスキー的キリスト教の思想的特質は何であるか? 》と。この問いは実は次の問題を含んでいる。では、世に幾つかの対立しあうキリスト教理解があるわけだが(少なくともすぐわれわれの眼を捉えるのはローマ・カトリック、プロテスタント、そしてロシヤ正教の三者である。ただし私の考察においては、そこにグノーシス派キリスト教とニーチェのイエス解釈が付けくわわる)、そのなかで彼のキリスト教理解は、そのどれをキリスト教の真髄から大きく背馳するものであるとして拒絶し、他方、或る解釈には基本的賛意なり親近感を抱きつつ、あるいは期せずしての一致を示しつつ、かくて激しくも鋭い如何なる解釈論争の内に自分を措定するものなのか?「ドストエフスキー的」という特別な形容が暗黙の裡に措定しているその固有なる対立者・論争相手とは誰か?
まさにこの点で、次の判断が彼のキリスト教理解の根幹を形成していることに注目しなければならない。すなわち彼は、ローマ・カトリックを、つまりは西欧の正統キリスト教の最大の潮流を、なんと、キリスト教の真髄をなすくだんの「イエス主義」(彼のいう「キリストの真理」)を裏切り、「キリストの真理」がこの地上において実現を果たすプロセスをどう展望するかという点で、本来のイエスの思想と真逆の発想を取ることでその実現を根幹的に不可能にする、憎むべき背教の徒とみなしたのである。他方彼は、ロシヤ正教を「キリストの真理」に最も忠実なる潮流と捉え、またプロテスタントは一見カトリックと激しく対立するように見えて、その本質において――ことにルターの不寛容なる自己絶対視と他者排除の暴力性において――ローマ・カトリックの権力主義的性格を分有するものとみなした。
では「真逆の発想」とはどういうことか? 詳細はまさに第一章に委ねるが、彼は次のような認識を披歴したのだ。ここで『作家の日記』での彼の言葉をもって示すならば、――ロシヤ正教は「まず最初にキリストを中心とする人類の霊的結合があり、そのあとで〔略〕その疑う余地のない結果として正当な国家的、社会的結合が生まれてくる」と発想したのに対して、ローマ・カトリックはまさにプロセスの順序を逆にして、ローマ法王を君主とする全世界を束ねる「強固な国家的結合」をまず生みだし、その強権をとおして次に「人類の霊的結合」を実現すべきだと発想した、と[7]。
だがドストエフスキーにいわせれば、そのような強権主義はまさにその強権主義によって人類の抱える暴力的対立を緩和させるどころかますます激化させるだけであり、それが必然的に生むことになる復讐の連鎖に全世界を巻き込んでしまうことで、「剣に立つ者は剣に倒れる」の格言どおり、「キリストの真理」の実現を根本的に不可能にしてしまう道でしかない。
しかも彼によれば、「自由・平等・友愛」をスローガンとして闘われたかのフランス大革命と、そのあとにこの革命理念のより徹底した実現を求める潮流として生じた社会主義運動、特にその「政治的社会主義」と呼び得る潮流は、右の観点からすれば、実はローマ・カトリックのいわば鬼っ子的継承者なのだ[8]。人類の真の兄弟愛に横溢した相互扶助共同社会を強権すなわち暴力革命によって実現せんとする点において。
第一章で再び取り上げるが、ここで二つのドストエフスキーの言葉を紹介しておこう。先に私はドストエフスキー的キリスト教の一つの特質を、それが「受難した子供の眼差し」で人間社会を見渡す点にあることを強調した。次に紹介する言葉――それは『カラマーゾフの兄弟』におけるイワンの人物造形について語ったものである――は、ドストエフスキーにおいて社会主義問題はこの特質の問題とも深く連関することを示唆する。いわく、
「社会主義は全体として、歴史的現実の否定から出発して、破壊と無政府主義のプログラムに到達したのです。根本的な無政府主義者たちは、多くの場合、真剣な確信を有する人々でした。小生の主人公は、小生にいわせれば、否応のないテーマ、すなわち小児の苦痛の無意義ということを取り上げて、そこから歴史的現実全体の不合理を演繹しているのです」(傍点、清)[9]。
彼は、西欧社会主義の受け売りになり下がったロシヤの「無政府主義者たち」・「政治的社会主義」を厳しく批判するにせよ、この彼らの誤りの根源には彼らなりの「受難した子供の眼差し」への熱き連帯の想いがあったことを見落とすまいとした。だからこそ、彼らの誤りはいっそうの悲劇性を示すと考えた。つまり、ドストエフスキーもまた社会主義者だったのだ。事実、彼は『貧しき人びと』で作家デビューした翌年(一八四七年)、当時ロシヤにおいて最もラディカルな社会主義サークルであった「ペトラシェフスキー・グループ」の一員となり、その二年後国家反逆罪を犯した罪で逮捕され、ただちに銃殺刑に処せられることとなる。周知のように、その処刑当日恩赦が下り、彼はシベリヤ流刑に付される。かかる来歴をもつ彼は、シベリヤ流刑を解かれた後、一方では西欧出自の「政治的社会主義」を厳しく批判しながら、他方、真の社会主義へ至る別の道の探求を始めるのだ。
紹介したいもう一つの言葉はまさにその点にかかわる。それは、暴力革命を必須のものと考える西欧の「政治的社会主義」に対置して、非暴力的なもう一つの社会主義の生成の展望をロシヤ民衆のエートスのなかに探ろうとする『作家の日記』のなかの言葉である。いわく、
「ロシヤの社会主義の究極の目的は、この地球が収容できる限りの地上に実現される、あらゆる国民を網羅する、全世界的な全民衆的な教会の樹立である。〔略〕ロシヤ民衆の社会主義は、共産主義ともちがえば、機械的な形式だけにとどまるものでもない。究極においてはキリストの名による全世界的な団結によってのみ救われるものであると、民衆は固く信じているのである。これが我がロシヤの社会主義なのだ!」(傍点、ドストエフスキー)[10]。
つまり真正の社会主義を実現する道とは、ロシヤ民衆のいわば無意識のなかに深く根を下ろした「キリストの真理」の生む共苦のエートスに依拠した非暴力的な精神革命の道、《「イエス」主義的なキリスト教的社会主義=ロシヤ民衆の社会主義》を追求する道なのだ。第一章において詳論するが、この構想は、「キリストの真理」の生む共苦のエートスの社会組織的裏付けをロシヤ農民の内に相当なる民俗的強度をもって持続している「土地共同体」のエートスに見いだすものであり、この社会的エートスを最大限に賦活せしめることによって、強権の道を通らず社会主義的社会改造を成し遂げようとする道なのだ。かかるものとして、この路線は、他方の路線、すなわち前衛的分子によるほとんどテロリズムと大差ない強行的な暴力革命の遂行、それによる地上の国家権力のクー・デタ的奪取、それをとおしての社会組織の上からの強権的な社会主義的改造の完遂、この展望に一切を賭ける「政治的社会主義」の前衛党主義に立脚する暴力革命路線に厳しく対置される。
注目すべきは、彼の脳裏のなかでは前者の依拠するロシヤ民衆の「土地共同体」エートスは次の点で精神史的な宗教文化的奥深さをもつと捉えられたことである。すなわちそれは、キリスト教渡来以前から保持されてきた農民のアニミズム的な起源をもつ汎神論的大地信仰に根を下ろし、それと一つに縒り合わさった宇宙観的強度を備えた宗教感情的性格をもつエートスなのである。つまり、かのドストエフスキー的キリスト教の第二の特質に見事に呼応するそれなのである。そしてこうつけくわえておきたい。まさにこうした問題への視界は、彼がかのシベリヤ流刑をとおして身銭を切って得た民衆経験と、そこから発するロシヤ・インテリゲンチャたるおのれへの自己批判、それが生みだした視界であったことを。
実は、私は先に紹介した『聖書論Ⅰ』の補注の最後をこう結んでいた。
「しかも、『罪と罰』は『分離派』信徒であるソーニャの形象を媒介にして、右の『憐れみの神』の思想をキリスト教渡来以前からロシヤ民衆に染みわたっていた大地母神信仰と意識的に結びつけ、逆にそれをラスコーリニコフの形象に孕ませた終末論的救済の『聖戦』思想の系譜――古代ユダヤ教の預言者伝統と『ヨハネ黙示録』を繋ぐ――に意識的に対置せしめる。まさにこの点においても、私のイエス理解と呼応するところ大である」[11]。
その詳細は第一章に譲るが、右に縷々述べてきたドストエフスキーにおける社会主義との葛藤的関係、彼が「政治的社会主義」と名づけた西欧の社会主義暴力革命思想と彼が社会主義の真正の道と考えた《「ロシヤ民衆の社会主義」=「イエス主義」的キリスト教社会主義》の道との葛藤、このテーマは彼の後期五大長編世界を決定的な仕方で貫いているのだ。注意深く読めば、ラスコーリニコフは「政治的社会主義」の確信犯として登場するのであり、くだんのローマ・カトリックのなすイエスの本来の思想からの背教は『カラマーゾフの兄弟』の白眉の一つたるかの「大審問官」章のテーマそのものにほかならない。ロシヤに移植された西欧の社会主義暴力革命思想がその民衆からの乖離=「地盤喪失」から必然的にテロリズム化する成り行きはまさに『悪霊』の主題であるし、ローマ・カトリック批判の言説は注意深く読めば『白痴』においても『未成年』においても主人公たちの思想の核心にかかわる問題として顔を出している。
しかもこの二つの路線の対立関係は、ユダヤ=キリスト教の宗教文化史的伝統それ自身と骨絡みとなった対立を背景にもつ。一言でいえば、『ヨハネ黙示録』の深部にまで継承される旧約聖書のヤハウエ主義的革命主義・「聖戦」思想(マックス・ヴェーバー)と、明らかにこの精神伝統から、しかし、その強烈な自己批判として誕生するイエス主義(「愛敵」と「赦し」の思想)との相克という問題背景、これである。私はこの件に関しては本書の終章「ドストエフスキーと私の聖書論」に詳しく述べた。
かくてくりかえすなら、本書第一章は他の諸章と有機的に関連し、その有機的全体性を観望する扇の要の位置を占めるものなのである。その位置からドストエフスキーと社会主義との関係性を問おうとするものなのである。(なお、次のことを注記しておく。これまで述べきたった問題の他の側面とは、私が第一章で取り上げた次の問題、すなわち彼の「犯罪」論が如何に彼の「社会主義」論ならびに「イエス」論と切り離しがたく結びついて展開されるかという問題なのである。このような三者関係が強力に構成されること、それ自体が如何にもドストエフスキー的なのである。)
この「はじめに」を結ぶにあたって次の二点をつけくわえておきたい。
第一点。私は以上述べきたった私の論点をできる限り尖鋭かつ鮮明なる形で読者に届けたいと思い、本書の幾つかの節や補注をとおして、それら論点を江川卓氏と山城むつみ氏のドストエフスキー論への批判と縒り合せて提示すべく試みた。
江川卓氏の「謎とき」ドストエフスキー解釈の起点となった『謎とき『罪と罰』』は読売文学賞(一九八七年)を受賞している[12]。また山城むつみ氏の『ドストエフスキー』は毎日出版文化賞(二〇一〇年)を受賞している。この点で、この二冊は今日の時点における現代日本のドストエフスキー論の二つの代表である。(以下、敬称は略する)
しかし、私の見地からすれば、彼らのドストエフスキー論はドストエフスキー文学の本質に迫るうえで大きな不満を残すものでもあった。私は、その不満を率直に述べることが、ドストエフスキー文学の本質ないしはそれが孕む偉大な問題性に迫るうえできわめて興味深い特別な回路――まさに両者への批評を媒介にするからこそ開ける――を形づくると考えた。また私は、およそ評論者はそうした論争・討論・対話の公開的磁場を読者の前に形成する社会的義務を負っていると考える。
第二点。本書にとってニーチェの存在は特別な重要性を、まさに議論媒介者としての決定的な位置を獲得している。先に述べたように、ドストエフスキー的キリスト教の思想的特質を問うとは、西欧においてそれまで正統キリスト教として登場していたローマ・カトリックのキリスト教理解をドストエフスキーが決定的に疑問に付したという事実、その意味を問うことと一つに縒り合さっていた。
ところで、拙著『聖書論Ⅰ 妬みの神と憐れみの神』と『聖書論Ⅱ 聖書批判史考』は従来「正統キリスト教」と遇されてきた教説に孕まれる問題性を批判的に検討するという作業を随伴するものであった。そして、私の検討作業の機縁となったのはまさにニーチェの「正統キリスト教」批判であったのだ。彼は、そもそも正統キリスト教とイエス自身の思想とを真っ向から対立させ、前者をイエスの名を騙らってイエス自身の思想と真逆の思想を説き、イエスの古代ユダヤ教を乗り越えようとする試みを再び古代ユダヤ教へと先祖帰りさせるものとして批判した。私はこの彼の議論にいたく刺激された。しかも実はニーチェは、「ドストエフスキーこそ、私が何物かを学びえた唯一の心理学者である。すなわち、彼は、スタンダールを発見したときにすらはるかにまさって、私の生涯最も美しい幸運に属する」とまで述べた人物であった[13]。
私は、第三章ならびに第四章の幾つかの節において次の問題を徹底的に究明した。すなわち、ニーチェの遺稿「遺された断想」(白水社版『ニーチェ全集』第十巻)には『悪霊』からの実に丹念な書き抜きが残されており、それが彼の『反キリスト者』、『権力への意志』のなかの「宗教の批判」諸節、『偶像の黄昏』、等でのイエス理解と正統キリスト教批判と深く結びついているという問題を。ドストエフスキーを照らしだすうえでも、また逆にニーチェを照らしだすうえでも、この書き抜きが示唆する両者が結んだ思想の共振と反発の関係性は実に「十九世紀の西欧精神史上の一大事件」と呼び得る価値を有するものだ。そういうものとして、ニーチェの存在、とりわけ彼のドストエフスキーへのかかわりは本書の議論展開における最大の媒介者の役割を果たすのである。
最後にこう申し添えておきたい。本書においては、五大長編と『作家の日記』を渉猟することによって得られた成果の記述は、その生成の経緯を反映し、『罪と罰』、『悪霊』、『カラマーゾフの兄弟』の三作品の考察を基軸に据えてなされるものとなった。『白痴』と『未成年』および『作家の日記』の三作品に関しては、私はその基軸となった議論にそれぞれがどのように絡むかについて論じた節を各章に適宜添えることにした。いいかえれば、もし読者がそれぞれの作品をテーマに立て、各章における当該作品に関する節を拾い読みしていけば、そこにおのずと各作品に関する私の評論のそれなりの全体像が浮かび上がるようにも構成したのである。
また、この後期長編世界の山脈がドストエフスキー文学の展開史のなかでどのようなそびえ方を示すかを少しでも示唆しておきたいという想いから、彼のデビュー作『貧しき人びと』と第二作目『二重人格』、ならびに彼のシベリヤ流刑体験を語る『死の家の記録』、そして一八六四年に最初の妻マリヤの遺骸を前にしてしたためられた「一八六四年のメモ」と、同じ年に書かれた『地下室の手記』、これらの作品についての論評を節・補注・補論等の形でつけくわえた。なお第六章「ドストエフスキーの小説構成方法論」は、彼の抱いた思想と人間観の内容がいかに彼の小説展開の形式を規定したか、内容における「ドストエフスキー的なるもの」は如何に形式におけるそれとなって現れたかを考察した章である。また終章を結ぶにあたっては、本書とそれに先立つ私の『聖書論Ⅰ』・『聖書論Ⅱ』との関連が読者に明確に伝わるように工夫した。この終章は彼の社会主義論と深く関連するだけでなく、彼の性愛論とも深く関連する。私は相当に詳しくグノーシス派のプラトン主義的ないわば性のユートピア・エロスのユートピアを紹介し、それと彼とを対比することをとおして、彼には性的快楽に関するユートピア的次元が欠落していることを析出した。
江川卓氏と山城むつみ氏への批判、そのいくつか(以下、敬称を略す)
江川卓は如何にドストエフスキー文学に「分離派」に対する強い関心が反映しているかを、おそらくこれまでのドストエフスキー解釈が及びもつかぬ斬新な解釈を披歴することで問題提起した。このことは確かである。
しかし私からいえば、この「分離派」問題(それが孕む「大地信仰」問題)がキリスト教的社会主義の可能性を探求し、他方、西欧の「無神論」的な「政治的社会主義」を厳しく批判するというドストエフスキーの思想的立場に如何に深く内在的に結びついているかという肝心な問題、これについては彼は唖然とするほど無関心なのである。またこの無関心が災いして、「カラマーゾフ的なるもの」に関する彼の理解は実に浅薄で平板きわまるものなのだ。
既に、私は本文のなかで「カラマーゾフ的天性」をドストエフスキーがどのようなものとして描きだしたかについて相当詳しく述べたが、江川は『謎とき『カラマーゾフの兄弟』』において「カラマーゾフ的」とは如何なる特質を指すか? という問いを自ら立て、「まず第一にあげられる特質は『好色』である」と述べ、そのうえで、その「好色」は「ただのみみっちい」それではなく、激烈な、「生への渇望」と結びつき、さらにまた「放蕩の恥辱」の「奈落の底」へと自ら飛び込むような、またそこに美を見いだすような耽美的で背徳的な性格をもつものだと指摘している[14]。しかし私にいわせれば、この定義では、「カラマーゾフ的天性」の秘める矛盾的ダイナミズム、まさに『悪霊』のワルワーラ夫人のいう「反対極への渇望」がドストエフスキー文学全体に果たすいわば領導的役割、これを全然掬い取ることができないことは明らかである。なお、私は次の第一章の補注において、如何に彼がドストエフスキーと社会主義との関係性に対する問題意識を欠いているかを縷々批判するであろう。
では次に、山城むつみに対する私の不満はどこにあるか?
彼のドストエフスキー解釈はミハイル・バフチンのいう「ラズノグラーシェ」(同意したいからこそ反発するというアンビヴァレントな力学が生む、不同意)の関係性を読解の導きの糸とすることで成り立つ。それは幾多の点で啓発的である。特にバフチンへの高い評価は私の共感を誘う点を多々含んでもいる。
とはいえ、やはりドストエフスキー文学の本質的な問題性を主題化することに失敗している。たとえば彼はこう書く。「アウシュヴィッツをもたらした悪の真の恐ろしさは、それがサタニックなものではなく、バナールなものだった点にある。〔略〕アーレントはアイヒマンのうちに想像力の欠如(命令を唯々諾々と陳腐なまでに実行し処理したこと、清)を見出したが、ドストエフスキーならさらに危険を犯して、そこに人間的な善意を見出すだろう。出来した悪の悲劇的なあまりに悲劇的な恐ろしさと、その責任者の人間的なあまりにも人間的な善意との間のこの喜劇的なあまりにも喜劇的なギャップこそ真に恐ろしい、と。〔略〕それは事実そのものが内包している逆説だ。歴史が常に秘めているパラドックスである。我々が今日、ドストエフスキーを読む意味はそこにある」(傍点、清)と[15]。
だが私にいわせれば、そのような「喜劇的なギャップ」なぞがドストエフスキー文学のテーマであるわけもなく、この程度の「歴史が常に秘めているパラドックス」に夢中になるセンスでは、およそドストエフスキー文学の抱える本質的な問題性に感応することはできない。いったいそこに登場する主人公と副主人公たちがどうして「サタニックなものではなく、バナールなもの」によって特徴づけられるといい得るのか? 『作家の日記』のなかでドストエフスキーは「ロシヤの民衆の最も根本的な精神的要求は――場所と対象を選ばぬ、飽くことを知らない不断の、苦悩の要求にほかならない」と述べた[16]。実に、ドストエフスキー文学の主要な登場人物は例外なく「苦悩の要求」によって駆動され人生を生きる人物たちなのであり、「良心の呵責」こそは、ドストエフスキー的キリスト教の決定的な繋留点なのだ。何故、サド=マゾヒスティックと形容すべきほどに「良心の呵責」に七転八倒する人物がバナールなのか? むしろサタニックであることは明白ではないか? 事実『カラマーゾフの兄弟』の第十一編九章「悪魔。イワンの悪夢」は、譫妄状態に陥ったイワンの前に、彼の内なる《もう一人の自分》が「悪魔」という分身となって外在化し出現する場面を描く。この章は「反逆」章や「大審問官」章と並んで同小説においてイワンがいやがうえにも際立つ白眉の章の一つである。しかも既にして『未成年』において、その副主人公ヴェルシーロフの人格性(実存構造)を象徴するキーワードとして「分身」(悪魔的な)が登場するのだ(本書第五章・「『未成年』における愛と嫉妬……」節[17]。なお、トーマス・マンの『ファウスト博士』第二五章――主人公のアドリアンがおのれの分身たる悪魔と交わす対話をしたためた――は、おそらくそれを先行モデルとしているにちがいない[18])。
私見では、山城の視点のこうした平板さは、彼のドストエフスキー論では「ドストエフスキーと社会主義」というテーマが――第一章の補注で縷々述べるが――長編諸作品の内容に立ち入った形ではほとんど論じられていないことと相関している。また、ドストエフスキーが、常に怨恨人の抱え込む内面的苦悶の鋭利な切開こそを彼の文学的焦点にしてきた事情、その深い意味を十分に掬い取っていないことに。
[1] 原卓也訳『カラマーゾフの兄弟』、下、新潮文庫、四七六頁
[2] 江川卓訳『悪霊』上、新潮文庫、三六三頁
[3] 江川卓訳『悪霊』下、新潮文庫、五二四頁
[4] 工藤精一郎訳『未成年』下、新潮文庫、二〇〇頁
[5] 拙著『聖書論Ⅰ 妬みの神と憐れみの神』の第Ⅱ部「イエス考」・補注「《人間の根源的弱さへの憐れみの愛》の思想とドストエフスキー」、藤原書店、二〇一五年、一六九~一七〇頁
[6] 江川卓訳『罪と罰』上、岩波文庫、一九九九年、五三~五四頁。なお今日ミハイル・ブルーガコフはスターリン治下のソ連における最大の作家と目されているが、彼の最高傑作とされる『巨匠とマルガリータ』(水野忠夫訳、岩波文庫、二〇一五年)には、主人公の作家が創作したとされる小説がいわば《小説内小説》として登場する。それはイエスの磔刑死を頂点に据えた、イエスとマタイと当時のユダヤ総督ピラトゥスとの対話劇として書かれる。あたかもかの「大審問官」章の如く。そのさいブルガーコフはイエスの思想の核心を、罪人を「病者」に神を「医者」に擬し、「憐れみの愛」を病める人間(=罪人)への最大の治療薬とみなす『マタイ福音書』のイエス解釈に設定している。だからこの《小説内小説》にあっては、マタイがイエスに最後まで付き従い、彼の遺骸を独りで密かに収容し埋葬した、イエスの最も忠実なる弟子として登場する。同小説ではドストエフスキーが《作家》を象徴する存在として讃えられる。私は右の問題設定自体がドストエフスキーから汲み取られたのではないかと推測する。参照、同書・上巻、四九~五四頁、
[7] 小沼文彦訳『作家の日記』4、ちくま学芸文庫、一八八七年、五・六月号・第三章、四三二~四三三頁
[8] 同前、四三四、四三七頁
[9] ドストエフスキー、米川正夫訳『書簡』、ドストエフスキー全集18、河出書房新社、一九七〇年、二八〇~二八一頁。
[10] 『作家の日記』6、一八八一年一月号、一八六~一八七頁、『カラマーゾフの兄弟』下、六七六頁、原卓也の解説にも引用されている。
[11]拙著『聖書論Ⅰ 妬みの神と憐れみの神』の第Ⅱ部「イエス考」のなかの補注「《人間の根源的弱さへの憐れみの愛》の思想とドストエフスキー」、一七〇~一七一頁
[12] 江川卓の「謎とき」ドストエフスキー解釈シリーズは以下のとおり。『謎とき『罪と罰』』、『謎とき『カラマーゾフの兄弟』』、『謎とき『白痴』』(出版順)、いずれも新潮選書。
[13] ニーチェ、原佑訳『偶像の黄昏 反キリスト者』ニーチェ全集14、ちくま学芸文庫、一九九四年、一三八頁
[14] 江川卓『謎とき『カラマーゾフの兄弟』』、新潮選書、一九九一年、一八~一九頁
[15] 山城むつみ『ドストエフスキー』、講談社、二〇一〇年、八五頁
[16]『作家の日記』1、ちくま学芸文庫、一八七三年・第五章、一〇二頁。江川卓訳『罪と罰』下、岩波文庫、訳注二〇九、四〇七頁。
[17] 工藤精一郎訳『未成年』下、新潮文庫、四八二、四八五、四八七‐四九一頁
[18] 参照、拙著『否定神学と《悪》の文学Ⅱ マンの『ファウスト博士』とニーチェ』アマゾン・kindle電子書籍、セルフ出版、第四章「人間的相互性への欠如的苦悩とマゾヒズム」。なお、同書でも触れているが、マンはドストエフスキーの文学を「地獄的な魂の状態に通じたキリスト教的な知識の世界」と呼び重大な関心を示している。私見では、彼の『ファウスト博士』へのドストエフスキーの影響はくだんの第二五章にとどまらず、主人公のアドリアンが交響カンタータ『ファウスト博士の嘆き』を最後の作品として作曲するというプロットにまで及んでいる。『未成年』のなかに、後に首吊り自殺するアンドレーエフがドルゴルーキーにこう語る場面がある。――自分は音楽好きであり、もしオペラを作るとしたら、きっとゲーテの『ファウスト』を取り上げ、グレートヒェンのおのが罪の赦しを乞うもそれを得れない苦悶をテーマとし、それを表現すために「いたましい叙唱」に「悪魔の声、悪魔の歌」が混じり合い溶け合って、最後にそれが「さながら全宇宙の喚声」の如き神を称える「ホザナ」の喚声によって結ばれるようにしたい、と(『未成年』下、三二六~三二八頁)。この彼の構想は、その本質において、実にアドリアンの『ファウスト博士の嘆き』とそっくりなのだ。推察するに、マンはこの『未成年』の一節から多大なるインスピレーションを得たのではないか?
![]() ――序に代えて
――序に代えて
この叢書は「否定神学と《悪》の文学」と銘打たれている。現在刊行されているのは三巻、第Ⅰ巻『預言者メンタリティーと『白鯨』』、第Ⅱ巻『マンの『ファウスト博士』とニーチェ』、第Ⅲ巻『ドストエフスキー的なるものと『罪と罰』』の三冊である。将来私は、この叢書の一冊として、文字通り『否定神学と《悪》の文学』というタイトルの評論を刊行したいと考えている。そこでは、この叢書の依って立つ視点がキリスト教神学の歴史に対する考察と縒り合せて論じられるはずであり、このテーマが西欧思想史、とりわけて十九世紀末から今日に至る近現代西欧文芸史のなかで占める意義が考究されるはずである。つまり、この視点が問題に接近する如何なる角度を意味するかの本格的な論述はそこで与えられるであろう。
ここでは次のことだけをいっておきたい。
通常、「否定神学」という用語は六世紀頃のキリスト教神学者、偽ディオニュシオス・ホ・アレオパギテースの著した『神名論』や『神秘神学』に由来するものであり、この用語によって示された思想とは一言でいえば次の主張であったとされる。いわく、世界の創造主たる神は人間の思考しうるいかなる「善」をも超えた偉大さにおいて善の源であるが故に、神という究極の善は事柄を「…である」と肯定的に規定する一切の人間の言語表現(=述語)の彼方にあり、むしろ「…でない」という否定表現が指し示す概念間の「闇と沈黙」の内に、裏返しにいえば「すべてを超えた光」の内にただ直観することだけができるものとして理解されるべきであると。この主張は特にキリスト教神秘主義の思想家たちに大きな影響を与え、たとえば、エックハルトは、放下(Gelassenheit)をとおして「名前無き無」としての神との合一が追求されるべきだとし、またクザーヌスはこう主張した。すなわち、神は万物の原理であるが故に、神の意思は被造物である人間の知をつねに超えている、だから神の人間に対する本質はまさに「知解され得ない」ことにあり、この神に対する人間の本質的な無知を自覚することこそが人間にとって最上の知、「知ある無知」であると。
私の刊行するこの叢書のタイトルに使われる「否定神学」とは、この元来の用語的意味ともちろん無関係でなく、そこから派生するものであるが、しかし文字通り同じとはいえないかもしれない。その辺りの詳細は将来刊行されるはずのくだんの一巻に譲ろう。要は私はこういう問題の連関を頭に浮かべているのである。
第一巻の考究対象であるメルヴィルと『白鯨』、第二巻のトーマス・マンと『ファウスト博士』、第三巻のドストエフスキーと『罪と罰』、いずれも、善の源であるはずの神の存在を、その神の意思を到底把握し得ない現世の人間界で出会う《悪》――対象としても、また自己自身の内なるものとしても――への痛憤と悲嘆を、しかし自分にとっては唯一のかけがえのない身銭を切った経験の証として差し出すことで、まさに否定しようとする。まさに「神はいない」という否定言明は《悪》の文学から生まれてくるのだ。否、むしろこういうべきだろう。彼らの《悪》の文学はなによりも神の存在の否定言明をなすためにこそあると。だが、彼らの文学のこの神学的性格には実は次の逆説、「神はいない」ということをとおしてしか「神はいる」という肯定言明はなし得ないという逆説、まさにくだんの「否定神学」に類似した逆説論法が潜んでいるのではないか? そして、この神学的性格を帯びた《悪》の文学の追求こそが近現代西欧文学史の核心なのではないか?
我が叢書を「否定神学と《悪》の文学」と銘打つ所以である。
目次
叢書・否定神学と《悪》の文学――序に代えて
はじめに――憐れみの愛と新生
第一章 自尊心の病、あるいはラスコーリニコフの「犯罪権」論
補注 『悪霊』とニーチェ
第二章 根本的感覚変容――意識と無意識との対話
第三章 少女凌辱――受難した子供の眼差し
第四章 犠牲
補注 スタヴローギンの二重人格性をめぐる
もう一つのくだり
第五章 ロシア民衆の神――ザロメの視点からも
結びに代えて
目次
叢書・否定神学と《悪》の文学――序に代えて
はじめに
第一章 アドリアンとなったニーチェ
第二章 マンのいう「市民的ヒューマニズム」
第三章 弁証法的弁神論
第四章 人間的相互性への欠如的苦悩と
マゾヒズム
第五章 『ファウスト博士』における
『ヨハネ黙示録』
第六章 「肉」の思想
第七章 アドリアンの告解と
「魔神的(デモーニッシュ)なるもの」
第八章 「ドイツ的なるもの」
――講演集『ドイツとドイツ人』を軸に
第九章 「ドイツ的なるもの」と音楽
補論 マン・ヴァーグナー・ニーチェ
目次
叢書・否定神学と《悪》の文学――序に代えて
はじめに
第Ⅰ部
第一章 最初の問い――巨怪なるものへの意識
第二章 預言者的心性、その英雄主義的・苦行僧的マゾヒズム
第三章 女性は誰も登場しない、ホモソーシャルな世界
――イシュメールとクィークェグ
第四章 『白鯨』における神と檣頭当番の汎神論的宇宙観
第Ⅱ部
第一章 敵対者の同一性
第二章 白色の形而上学
第三章 原始的光景への志向性と、そのアメリカ的基盤
第四章 東洋的宇宙館への傾斜
第五章 《受難した子供》としてのエイハブ
![]()
アマゾンKindle電子書籍個人出版
「総序――聖書論上・下巻をつなぐ」からの抜粋
四者のあいだの亀裂と対立、その緊張関係の理解なくしてどの一者の真の理解にも達し得ない。ここでの四者とは、旧約聖書に体現される古代ユダヤ教におけるヤハウエ信仰(マックス・ヴェーバーのいう「純粋ヤハウエ主義」)、新約聖書に語り伝えられるイエスの言葉と行為が推測せしめる彼自身の思想、パウロを創始者とする西欧の正統キリスト教、ならびに旧約聖書とイエス思想との対立性を徹底的に主張し、それを糊塗するものとして正統キリスト教を批判してやまなかった古代キリスト教における最大の異端たるグノーシス派、この四者を指す。 [略] これら四者のあいだに張り渡された抗争の関係は、確かにその一部分はこれまでも問題にされてきたものではその総体的な関連性の全景を浮かび上がらそうとする試みが十分になされたことはおそらく一度もない。 [略]
ではそれなら本書の意図するところは何か? 一言でいえば、たとえまだ拙い試みであるにせよ、右に述《四者の抗争関係》の総体的考察へと向かうための一個の作業ノートの提出の試み、これである。そのさい、本書は考察の土台をなによりもまず両聖書の言説の徹底的な分析作業に置く。そしてこの読解の一歩一歩の行程がおのずとその背後に、冒頭に述べた《四者関係を問わずしてはどの一者の真の理解にも達しえない》という問題の連関、いわば四者の
ところで、そのさい私には一つの試みてみたい視点があった。その視点とは、バッハオーフェンに始まり、日本では「文化圏的歴史観」を提唱し然混淆化という問題を伴う――というコンテクストを基軸に考察するという観点である。同時にまた、日本人研究者として私は、本書の試みにおいて、かの西田幾多郎の宗教哲学上の思索の営為を考察のなかに取り入れたいと思った。というのも、『善の研究』に始まり最晩年のほとんど彼の思想的遺書としての意義をもつ論考「場所的論理と宗教的世界観索の軌跡は、前述の《四者の抗争関係》解明に対する日本の地からの特別な側燈・フット・ライトとしての意義をもち得ると確信したからである。
私は新旧両聖書の言説そのものに密着した読解作業に取りかかった。一言注記しておくなら、その読解作業はヴェーバーの『古代ユダヤ教』を重要きわまる参照軸に据えることでなされた。 [略] 私は彼の考察を絶えまなく私自身の立てた問題構成のうちに組み入れ直しながら旧約聖書を読み、かつその作業の上に新約聖書の読解を組み立てていった。そして今後の自分の思索を導く作業仮説の確立を見た。それを一言でいうなら、《イエスの教説は、古代ユダヤ教の体現する父権的遊牧民的上天神的宇宙観の担うコンテクストからいえば、決定的でないにしろ、母権的農耕民的大地母神宗教への或る種の回帰であり、後者がいわば自然発生的に帯びているアニミズム的宇宙観への復帰の側面をももつ」》ということになろう。
その後のことである。私がこの自分の読解方法に接触してくるさまざまなる研究書を漁り、またグノーシス派のナグ・ハマディ文書の
評が集となった
。
目次
第一章 ニーチェのイエス論
第二章 フロイト『モーセと一神教』を読む
第三章 ユング『ヨブへの答え』を読む
第四章 オットー『聖なるもの』を読む
第五章 西田幾多郎と終末論
目次
総序――聖書論Ⅰ・Ⅱ巻を繋ぐ
〈付論〉石田英一郎の「文化圏的歴史観」と聖書世界
第Ⅰ部 妬みの神
第一章 嫉妬と熱愛
第二章 嫉妬の心性と旧約聖書
――『エレミヤ書』と『エゼキエル書』をめぐって
第三章 ヤハウェ主義を特徴づける女性嫌悪、あるいはその「肉」メタファー
第四章 母権的宗教に向けられた父権的な妬み
第五章 補助線としてのジェーン・ハリソン『ギリシアの神々』
第六章 「残酷な試しの神」としてのヤハウェと預言者のマゾヒズム
第Ⅱ部 イエス考
第一章 イエスというコペルニクス的転回
――発展的転換か、対立か
第二章 イエスにおける慈悲の愛の構造
第三章 イエスにおける「天の王国」表象の「生命力」メタファー
――種子と幼子
第四章 イエスの「姦淫」否定の論理
第五章 女性嫌悪に抗するイエスとグノーシス派
――グノーシス派文書『この世の起源について』と『魂の解明』にかかわらせて
第六章 イエスの生命主義とグノーシス派
補章 脱・預言者、反ヤハウェ主義者としてのイエス
| 聖書論Ⅰ&Ⅱ 藤原書店 |
![]()
362頁 4,200円

あとがきに代えて
ジジは煩悶するブンに応えるだろう。
答えなんかないねん! あるのは、バトン・リレーの試み。「歌われなかったことこそを歌にするという」挑戦。そして景色、記憶に刻まれた景色、ほとんど肉体に染み込んだ景色。それに、やっぱり捨てられへんのは歌の肉体性や! 声と歌う肉体!
その景色が、その声を引き出す。その声は、その肉体の揺れやしない方からしか出てけえへん
ブンがいう。
これまで歌われなかった歌、歌われても遠い昔だったり、どこかの目につかない片隅だったり、そこでしかまだ歌われていない歌、しかし、本当はそれこそが歌われるべき歌、その歌に出会ったとたん「リアル!」と思わず魂が叫ぶ歌。
そんな歌を歌おうとするシンガー・ソングライターの挑戦の歴史を追ってみたかったんだ。
ふたたびジジがいう。
バトン・リレーなんよ、歌は!
ブンは呟く。
ジョン・レノンから遠く離れて、マイケルから遠く離れて、ボブ・ディランから遠く離れて、関西フォークから遠く離れて、森田童子から遠く離れて、ポール・マッカートニーから、マルタ・クビジョバから、ロドリゲスから、汪峰から、ヘドウイックから、ブランキー・ジェット・シティーから遠く離れて、だけど、「そこから遠く離れて」という想いがそこに俺をつなげる、そういう仕方で、バトン・リレーのポジションにつくんだ。新しい歌は!
ジジがいう。
ブンのゆう半径3メートルのライブ空間をきっちり抱えたライフ・スタイル、そのめげへんヴィジョンこそ鍵やと思う! 吟遊詩人、物語作者、シンガー・ソングライターがふたたび歩き回りだすんや! 半径3メートルの小さな波紋がジワリまたジワリ! めげへんヤツラとゆわれたい!
Well, they'll stone ya
when you're trying to be so good
They'll stone ya
Just a-lile they said they woud
they'll stone ya
But I woud not feel so all alone.
Every body must get stoned.
ソング論
1Nothing is real
1 MOTHERと MY MUMMY’S DEAD
1 ロックンロールが鳴り止まないっ
1 カッコイイの原光景
1BAD
1 シンガー・ソングライター・スピリッツ
3 ジジとブンの替え歌遊び
1 犬より吠えた景色
1 ブルース・テイスト
3 ライブをもつ暮らしのスタイル
1「ぼく」と「君」の世界
――ヘイ!ジュード、シュガーマン、存在
1「歌」を歌う『ヘイ! ジュード』
3 なぜ『シュガーマン』が反アパルトヘイトの抵抗歌になったのか
4 汪峰の不幸と幸福、そしてわれわれ
第Ⅺ章 エロスの神話と引き裂かれた魂
――ロック映画『ヘドウィック&アングリー・インチ』から
1『愛の誕生 ORIGIN OF LOVE』
3 欠けていることの痛みは統一への憧れ、憧れは既に…
1 教室の景色
1 神聖かまってちゃんの自殺願望曲
3 方法論的ミスマッチ
6 『虚構アンダーグラウンド』
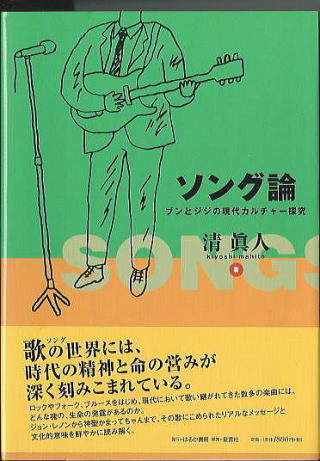
はじめに
武下和平さんは、戦後の奄美大島で「百年に一度の
歌が人の心を捉えるのはまずなによりもその歌手のえもいわれぬ独特なる美声、声の魅力を通してだといわれる。奄美ではそのような魅力的な声をもつ唄い手のことを「
だが、ただ声者だけではまだ「唄者」とは呼ばれぬ。シマ唄はまさに民謡として、
しかし、唄とは同時にまた音、つまり曲であった。リズムであり、メロディーであった。しかも、聴く者の心を弾ませ、踊らせ、きしませ、唸らせるためには、唄い手が差し出すその心の上げ下げ、「
「唄者」とは、声者・ねィんごう者・ぐいン者の三者を一身に兼ね備えた唄い手を、ただそうした唄い手だけを、呼ぶ言葉である。
武下和平さんは奄美の幾多の唄者の代表のような存在である。彼は昭和八年(一九三三年)に奄美大島瀬戸内町・加計呂麻島・諸数に生まれた。だから今年でもう八一歳になる。しかし、彼の声の艶は全然衰えていない。
彼が最初に出したレコードや、後に発売された青年武下和平の唄声が収録されているCDを聴くと、彼の声のキーが囃子方の女性の声のキーよりも高いことがよくわかる。奄美のシマ唄の日本民謡全体のなかで占める断突の個性は、男性が女性を上回るほどの高い声で女性の唄声に掛け合うところから発展してきた、その裏声唱法にある。日本ひろしといえども、この裏声唱法の冴えは唯一奄美だけに帰せられるものである。青年武下の声は、まさにこの点で断突であった。
そして、八十歳を越えたいま、彼の唄を聴くとき、人は、彼がまるで海に突きだした岬の岩盤のうえにただ独り座り、その大なる岩盤に彼の唄を命の水として打ち、また張る、それが彼の唄なのだと感じるであろう。また、その命の水、彼の唄声を得て、その岬の岩盤がにわかに艶を放ち、瑞々しく、また静謐なる光に包まれる、そのような光景を思い描くであろう。
彼は、十二歳のときに古仁屋の民謡大会に初出場したことを皮切りに唄者への道に旅立つ。二七歳で名瀬の奄美民謡大会に初出場し、そのとき、彼を最初に「百年に一度の唄者」と評した奄美シマ唄研究の第一人者の山田米三氏に見いだされ、翌昭和三六年に早くも文部省主催の「第十六回芸術祭全国民謡大会」に奄美チームの一員として出演する。そして、その翌年には名瀬のセントラル楽器から山田米三氏の多大な協力のもと最初のレコードを制作発売した。青年唄者武下和平の誕生であった。
それ以来、彼は日本全国に奄美シマ唄を紹介する奄美の代表的な唄者としての道を一筋に歩んで来た。そして昭和四九年(一九七四年)に「武下流民謡同好会」を発足させ、奄美シマ唄の伝統を脈々と継承する一大拠点として「武下流」を開いたのである。関西同好会と東京同好会を二大拠点とするこの「武下流」の活動は、本土に暮らす奄美出身者の望郷の念に火を放った。本土に奄美シマ唄をみずから唄い楽しむ伝統が移植された。そして、いわばそこから逆輸入するようなかたちで、奄美自身のなかにあらためてシマ唄の伝統を絶やすまいとする幾多の人々がこの「武下流」の活動のなかから育ったのである。
くりかえしいう。「唄者」とは、声者・ねィんごう者・ぐいン者の三者を一身に兼ね備えた唄い手を呼ぶ言葉である。
そういう唄者の、そのまた代表者である武下さんに、彼が生き通してきた唄者人生を、またシマ唄への想いを語ってもらおう、その彼の肉声は、わたしたちが奄美のシマ唄の世界、その宇宙へと近づき、そこへと身を浸すときの、なによりの案内人となってくれるに違いない。この想いが本書を産んだ。工夫として、まず第一章として「誌上シマ唄入門教室」を開こうということになった。本書において読者とは、同時に、武下師匠のお弟子さん、生徒さんである。
武下さんと私とのシマ唄をめぐる対話が進展してゆくにつれ、本書の意図にふさわしく、この本にはCDを付録として付け、そのCDによって、第一章の「シマ唄誌上入門教室」で語られた内容が実際の彼の唄を通しても味わえるようにしようというアイデアが生まれた。そこからさらに、この際だから、ぜひ奄美の祝い唄と教訓歌を一個の独立した章・第二章として論じ、またそれが武下さんの唄としても聴けるようにしようということになった。
奄美のシマ唄が実に豊富な数々の祝い唄に満ちているということは、シマ唄がいかに
武下さんは既に昭和四八年に一度「祝い唄集」のレコードを出そうと試みている。本書はその試みを四〇年を経て引き継ぐ。
奄美のシマ唄を島人は「半学」とも呼んできた。半分の学問、半分学問を兼ねているものという意味である。ここでいう「学問」とは、人生の学問、人生を正しく活き活きと情を濃くして生きるための知恵という意味である。読み書きのできなかった昔の島人は、それを唄にすることをもって親の子に対する教育とし、仲間同士の教育・学び合いとした。ここでもまたシマ唄は島人の生きるための魂の武器であり智恵であった。
第三部は、もう説明するまでもない。題名通り、たくさんのエピソードに満ちた武下さんの肉声が語る「唄者への道」回顧録である。幼年時代の貴重な記憶から始まる。「百年に一度の唄者」の言葉の由来も解き明かされる。読者が存分に楽しまれることを期待する。
二〇一四年三月 記 聞き手 清眞人
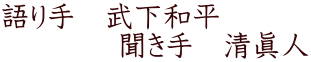

あらためてLは気づいた。キリスト教の物語は、幼いわが子を慈しむ母の喜びと、息子の死骸を我が胸に抱かねばならなかった母の絶望の、二つの極のあいだに張り渡されているのだということを。イエスに授乳するマリアの聖母子像と、十字架からようやく引き降ろすことのできたイエスの亡骸を抱くマリアのピエタ像の二つの扉こそが、この物語の二つの極をなすのだということを。事実Lは、ミラノのスフォルツェスコ城の博物館では、何に使うのか本立てのように向かいあった一対の二つの小さな扉が、一方は聖母子像を、他方は磔刑となったイエスの足下に悲嘆のあまり倒れ伏すマリアを描いているのを見いだした。
この一対性、希望と絶望が、幸福と身を噛む悲痛がたがいを照らしあうように結ばれているこの一対性、生命を生み育む母親であるからこそ担うこの一対性、それこそはキリスト教の物語の張り渡される図像学的な磁場なのだ。さまざまな物語が語られた果てに、すべてが忘却の淵に没し去った後も、始まりの扉と終わりの扉だけは残る。あたかもその物語をただ二言において要約するように。子を抱く母の喜び、母に抱かれる幼子の幸福と、子を残酷に殺害された母の絶望の一対性として。
ふとLは思う。無残に殺害された息子を我が手に抱かねばならない母の絶望は、そのいわば図像学的な真実性によってそのままキリスト教の
愚かしくも、Lはいまさらながら旧ユーゴスラヴィァがイタリアの陸続きの隣国であることを確認した。Lのペンはパレスチナを確認した。これから向かおうとするトルコにおいて、トルコ政府軍とクルド族の分離独立を求め武装闘争を呼号するクルド労働党との戦闘による死傷者は双方あわせてすでに一万数千人を越えるという、出発日に日本で読んだほんの数行の小さな新聞記事を思い出した。クルドのゲリラになる人物が出てきた、若くして死んだトルコの映画監督ギュネイの映画のことを思い出し、トルコによるクルド族の大虐殺について語ったLのイラン人の友人の話を思い出し、トルコの隣国のイランとイラクの悲惨極まりない先の戦争や、かつてはこの友人や、コミュニストのその兄が希望を託し命を捧げようとしたイラン革命と彼らの希望を打ち砕くこととなったその顛末を思い出し、また湾岸戦争を思い出した。到着した翌朝ホテルで見たイタリアの朝のテレビニュースは、チェチェンでのロシア軍とチェチェン市民軍との市街戦の模様を映していた。
キリスト教の絵画的伝統においては、聖母子をめぐる希望と絶望、幸福と悲嘆の一対の図像学的磁場には、それをいわば集団的に増幅するようなかかわりにおいて一つの物語が重ねあわされる。すなわち、ヘロデ王による幼児虐殺の図である。イエスの誕生を占星術によって知った東の博士たちより、「ユダヤ人の王とて生まれたまえる者は、いずこに在すか、われら東にてその星を見たれば、拝せんためにきたれり」との言上とともにその誕生を告げられたユダヤの王ヘロデは、イエスの誕生を自分の王位纂奪の危険と誤認して、遂にはイエスが生まれたとおぼしきベツレヘムの地の二歳以下の男の幼児すべての殺害を命じる。新約聖書の『マタイ伝福音書』に曰く。「ここにヘロデ…(略)…ベツレヘム及びすべてそのほとりの地方なる二歳以下の男の児をことごとく殺せり。ここに預言者エレミヤによりて言われたる言は、成就したり。曰く、『声ラマにありて聞こゆ、慟哭なり、いとどしき悲哀なり。ラケルおのが子らを歎き、子らのなきゆえに慰めらるるを厭う』」と。
この幼児虐殺のエピソードはくりかえし画家たちによって描かれた。それは画家たちの想像力を十分に喚起する題材であった。ブリューゲルを好む人なら彼が描いたこのエピソードを主題とした絵を忘れはしまい。雪空が重く垂れこめる北方の白い風景の真ん中に、槍を宙天高く垂直に立てた騎兵の一小隊が黒々と密集して画面全体を死の恐怖によって威圧するなか、村の家々に押し入った兵士が幼児をその母親の手よりもぎ取り、広場にて幼児虐殺が執行されてゆくのだ。それを見た人間の誰が、この絵をたんに聖書の物語の紙芝居的再現だと思うだろうか。ブリューゲルは彼の時代の暴行をこの聖書的題材に託してこの画面に描きいれ記録したのだ。誰もがそう確信するにちがいない。
シェーナのドゥオーモ美術館であったか、それとも国立
その一つはとりわけ大画面であった。画家はその情景を詳細を極めて描写していた。画面中央の一人の兵士の剣は、幼児の柔らかそうなふっくらとした左類を貫き右のこめかみからその切っ先を突き出していた。剣には鮮やかな鮮血が頬から染み出るようにして鍔元へと流れ始めていた。またたとえば、画面右下の老婆は両眼から涙を滴らせてただ宙天を仰ぐだけであり、その膝下には若い母親と幼児が朱に染まってすでにこと切れていた。幾人もの刃を振りかざした兵士と女たちと幼児たちとが、幾重にも入り組み折り重なっての阿鼻叫喚の地獄絵図が、鮮やかな鮮血とともにいかにも豊満で強壮なローマ風の肉体のぶつかりあうドラマとして描きだされていた。
幼児虐殺は実に古くからの人間の記憶にちがいあるまい。それは戦争とともにある記憶、人間の残酷さと復讐の渇望の象徴としてある記憶だ。
Lはユーゴの内戦にかかわって以前聞いた話を思い出した。民族的憎悪に凝り固まった狙撃兵は意識的に敵方の子供と老婆を狙撃するという。親の面前で無残にも子供を撃ち殺すことほど、相手の魂を切り刻み相手に絶望を強いる激しい憎悪の発揮はなく、そして、それはだからこそ暴力の地獄的循環の道を切り開く。まさしく、旧約のエレミヤ書や新約聖書にいうように「ラケルおのが子らを歎き、子らのなきゆえに慰めらるるを厭う」なのだ。そのようにして、「復讐には復讐を」の叫びをテロリストや凝り固まった原理主義者たちが誰はばかることなく口にし、それに少しでも反対し和解や妥協を説く者を裏切り者・内通者として粛正する絶好の「暴力の
図像学的に確保し担保し続けられるキリスト教の
![]()
或る友人がいう。
何を書くかよりも如何に書くか、それが問題! と。
すかさず僕は応じる。胸のなかで。如何に書くかという問いのなかで立ち上がる「何を書くか」という新たな問いがある。その書き方でしか書けない何か、それが問題だ! 内容と形式は、いましがた君がいったような仕方でいったん分離される。だが、その分離を通してこそ再び統一されるのだ。
こうして、僕はいわば半文学としての僕の哲学スタイルに行き着く。
探偵Lを設定することによって、僕は磁場を形成する四つのポイントを得る。
捜査対象たるニーチェ。三人称としての捜索者たる探偵Lと、一人称としてのもう一人の彼。そして、その全体を書いている僕。四つのポイントのあいだに磁力線が張られ、一個の磁場が成立する。磁場が成立するとは、そこにたくさんのものをぶち込める《場》が開けるということだ。一つの遊域が。
そう! 僕はたくさんのものをぶち込みたかった。一種のフリージャズのように、荒々しくノイズとなって、そこにたくさんのものが沸き立つべきなのだ。
何しろ二〇世紀はさまざまな希望の屠殺場となり、廃墟となって、二一世紀に引き渡されたのだから。聞き耳をたてれば、いまもまだ殺された希望たちの苦悶の声が、天蓋を外され、いまは頭上の青い虚無の大空を仰ぎ見るだけとなった廃墟の、下草に絡まれ埋められた柱や壁の狭間でかすかに響いている。
僕はまだ生きているが、この二一世紀に、二〇世紀人として死んでゆくだろう。
僕は、ニーチェ捜索をこの二一世紀の野原に突っ立っている廃墟「二〇世紀」を野外舞台として上演したかった。
そう! 舞台といってもよい。磁場のことを。
舞台=磁場がそこにしつらえられてこそ、たくさんのものに声が掛かり、それに応えてたくさんのものが舞台袖から登場する。
まず、ニーチェを捜査する探偵Lを歩き回らせたかった。TVの人気ミステリー・ドラマに登場する探偵たちが皆そうやっているように。ぐるぐる回りながら彼らは推理する。そうしなければ推理できない。
舞台があれば歩き回れる。舞台があれば歩き回わらざるを得なくなる。歩き回ってこそ、ニーチェを捜査する探偵Lの主観のなかに渦巻く感情と想念と記憶がやっと登場できるようになる。或る対象の捜査は、その対象を捜査する或る主観それ自身の捜査へとたえまなく反転する。磁場はこの反転を生成させ、その反転こそが磁場の形成を促す。
論理の裏側に潜んでいる感情と記憶と想念を引っ張り出したかった。
なるべく主観を消して、まして感情や、記憶の個人的編成だとか、極私的な出来事なぞもちろんのこと、そうした一切を舞台裏に引っ込ませることが哲学論文の約束のスタイルだとしたら、僕のやってみたかったことは、ちょうどその逆だ。そうした一切を舞台上に登場させ、それらとあれこれ衝突し、会話し、喧嘩しながら、ニーチェを捜査する探偵Lを舞台に立たせたかった。
なぜ、君自身ではなく、探偵Lなのか?
Lを立てることで、僕は僕を僕から引き離し、そこに隙間を差し込み、さらにそれを大きく広げ、遊域を産み出すことができる。舞台=磁場を!
二つの理由があった。
一つは、相手がニーチェだったからだ。彼は一個の迷路だった。迷路を捜索する探偵はおのれ自身の迷路を歩く器量をもってこそ推理も冴えるというものではないか? ニーチェの迷路性は、迷路的に自分を語る能力を、ニーチェを捜査しようとする探偵Lに与えてくれる。推理には元手というものが要るのだ。
ニーチェは指摘した。シェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』に寄せて、シェイクスピアと彼が描いた伝承されてきた歴史的人物ブルータスとのあいだにある「類似性と内密な関連」について。相手の漏らすちょっとした言葉の端、綾、顔色の動き、指先の戸惑い、端くれのエピソードも一個の暗示となって、たちまち直観が閃き、相手と自分とのあいだに横たわる或る類似した秘密を嗅ぎつける能力について、その能力が今度は自分とシャイクスピアとのあいだにも、イエスとのあいだにもあるのだ、と。そうニーチェはおのれを誇示した。
ニーチェと渡り合うためには、彼の迷路性とのあいだに「類似性と内密な関連」を発見し得る自分の側の迷路性がなければならない。それが元手だ。相手の迷路を推理するための。そしてこの迷路性は個人的でもあれば歴史的でもあろう。個人探偵Lの抱える迷路性と彼の生きた二〇世紀の迷路性との。
とてもじゃないが、僕はニーチェがシェイクスピアと自分との関係についてなしたような誇示を、ニーチェと自分に関しておこなう度胸はない。しかし、何事もチャレンジすることは成長の糧だ。僕はまだ成長したい。自分と自分の二〇世紀を迷路的に語る能力を鍛えたい。ニーチェを師匠として。半文学の哲学スタイルを追求したい。
ただイエスの磔刑像がヨーロパを旅する僕に与えた或る圧倒的な印象だけがあった。
しかし、いま本書を書き上げて振り返るならば、その元になった旅行記は一個の予告であった。予言であった。そこで表明された「磔刑像連想」はその後一八年の歳月を僕のなかで歩きつづけ、ニーチェに出会い、また本書が示すようにその他さまざまなる人と出来事に出会い、かくて二〇一三年の春に『大地と十字架』となって花咲いたのである。内容においてだけではない、方法においても。僕は「連想」をいわば方法へと過激化するために探偵Lを登場させたのだから。
この一八年のあいだのさまざまなる出会いと、それが促した思索を、そのすべてとはいわないまでも、ぶち込みたかったのだ。フリージャズのノイズのように。連想が連想を呼びセッションに入るような仕方で。僕は。
二〇一三年、春が匂いだす日に 清 眞人

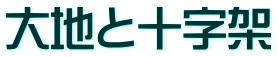
磔刑像連想
サンタ・マリアのフィレンツェ/ 観光客の眼 /磔刑像 /
ミュンヘンの「狩猟と釣りの博物館」/ ラ・スペコラ博物館
二重の仮面 /危険な神/ 遺構 / 大地を飛行する精のイマージュ
大地の道を往くことは窮境に至ることである/ 大地の道から逃げるな、歩き通せ!
宙吊りとは没落である
ニーチェを解毒することは彼を失うことである / ニーチェの毒性/ 変態と迷妄の断固たる自己肯定
「受難した子供」としてのニーチェ/ 内面化されし「境界石」すなわち「重力の精」
「墓の歌」章が告げるもの/ 怪物化した子供 / 『反キリスト者』におけるイエス像
反終末論
ニーチェとドストエフスキーを繋ぐ環としての子供主義 / 自虐の快としてのディオニュソス
没落(Untergang)というメタファー
大地の神は誰か? / Lは石田英一郎を助手として採用する
《死への欲望》の向かう先たる「根源的一者」――ニーチェの場合
ニーチェとバッハオーフェン / 戦士共同体のエートス/ 戦士的友情か母性的共苦か
ニーチェにおける女性性への隠された称揚 / 母なるものの不在
母権制の平和主義的心性 / ディオニュソス
敵として相まみえるニーチェとザロメ
今を取り逃がしたら二度とできないという想いで、本書を富島甫さんと作った。顧みれば、私が前著『
この夏の滞在で確かに私は直観した。奄美の人々の魂を知るための最大にして最深の道は奄美の歌謡文化のなかにこそ埋め込まれていると。しかし、まだそのときは三味線を楽器とするいわゆるシマ唄と小太鼓のティディムだけを楽器とする八月踊り唄との違いや相互の関係については、明確な理解はもっていなかった。その二つを一括りにして、とにかく私は、奄美の歌謡文化こそが――奄美の文化が連綿と呼吸してきた口承文化の強いヴォーカルな性格と一体となって――奄美文化の土台だと直観したのだ。
本書はこの直観の追求の書である。私はこの追求を為すうえで比類なきパートナーを得た。それが冨島さんである。
前著を出したとき奄美の主要新聞である南海日々新聞の或る幹部の方にこう聞かれた。「この本で何が一番書きたかったのか?」と。私は即座に「奄美の今を生きている人のことだ」と答えた。私は奄美についてのいわゆる民俗学的研究を書くのではなく、私が友達となった奄美の現在を生きる幾多の人間のことを書きたかった。対象を分析するようにではなく、まるで小説の主人公のようにその生ける姿で彼らを登場させたかった。本書においても然りである。私は何よりも富島甫さんを、彼が命懸けでその歌詞を残そうとした古仁屋の八月踊り唄とともに、書きたかった。
彼は学歴からいえば戦前に高等小学校を出て、そのあと内実は軍事教練に明け暮れただけの青年学校を出ただけの人である。しかし、彼は命懸けで古仁屋の八月踊りとその唄を記録し残そうとしてきた人である。もし、その彼の仕事がなければこの本はなかった。そしておそらく古仁屋のみならず、これほどの奄美八月踊りとその唄の紹介は誕生しなかったであろう。彼は今年九〇歳となった。彼は奄美八月踊りとその唄が現に集落の人々によって踊られ唄われ生きられていた、その姿を知る最後の生き証人なのである。彼の先輩のみならず同輩たちもあらかたもうこの世にいない。彼だけが生き残っているといって過言ではない。冒頭に書いた。繰り返す。今を取り逃がしたら二度とできないという想いで、本書を富島甫さんと作った。
奄美についての優れた民俗学研究書は幾つもある。しかし或る意味、それは、たとえどのように優れていようと、その優れた研究者の視角が切り取ってきた対象としての奄美文化の一側面を示すものに過ぎない。奄美八月踊り唄を現代標準語に翻訳し、奄美の
奄美のみならず、おそらくあらゆる真の民衆文化は冨島さんのような人間、民衆の一員として沸々たる断固とした「記録への意志」を生きた人間の存在によってのみ支えられるのだ。研究者ができることはその根元の事情を紹介することだけである。またそれが使命なのだ。
今、奄美群島全体が世界遺産に登録される機運が急速に湧き出していると聞く。奄美が世界遺産に値するのはたんに未だ観光地化されぬ、その自然の原初的輝きによってだけではないはずだ。奄美の自然は奄美の比類なき民衆文化の伝統と一体のものである。自然を離れて人間はないとすれば、同様に人間にとって自然は人間を離れてはない。魂に自然が染み込んでいることは自然に魂が染み込んでいるということでもある。自然と魂とが不離不即だという点にこそ奄美の文化の誇るべき原初性がある。つまり貴重な遺産性がある。その事情を端的に示すものこそが、万葉集の時代の「歌垣」=相聞歌の魂をそのままに永らく生き続けてきた奄美八月踊り唄なのである。
私は本書で八月踊り唄のこの本質的性格を「宇宙歌」とも名づけた。そこでは自然と魂とが切っても切れぬ一体性を結んでいるのであり、男女の相聞歌は、同時に集落が生きてきた親子の情愛を核におく心情の共有共感の全体に深く浸されているのだ。本書において事あるごとに繰り返し紹介したフレーズ、「踊らだなすりば、シマや荒れ果ててぃ、でい! 汝きゃんふり立てて踊て差上ろ」は、まさしく八月踊り唄の「宇宙歌」的性格こそが可能とする人間的生命の全体的高揚を表現する叫びである。奄美が世界遺産に値するとすれば、それはこの稀有な比類なき八月踊り唄の伝統によってもなのだ。そしてこの伝統のど真ん中では主体としての民衆が踊り歌っているのである。
末筆となったが、海風社の作井文子社長に心から感謝申し上げる。故作井満氏が奄美の文化と歴史的記憶を書物として残し、表現し、そうすることでさらなる探究を促進するために立ち上げたこの出版社の、その志を代表する「南島叢書」の一環として本書を、私の前著と同様出版してくださることは、私と共著者たる富島甫の名誉である。
![]()
清 眞人
奄美の八月踊りと唄は男女の掛合いをとおして踊られ歌われる。
それは、古代日本でおこなわれていたといわれる「歌垣」の世界をまっすぐに継承するものだが、この「歌垣」は
その方々の踊り歌う姿に接し、また彼らが強い意志をもって保存に努力してきた歌詞に触れると、私は、唄と踊りがその起源において日本人にもった深い人間的意味についてあらためて目を見開かされる。そもそも唄と踊りというものは本質的に掛け合いであった。そのことが発見として私にやって来るのだ。そして気づく。この事情は一見独演的に歌われ演じられることの多い今日の唄や踊りにあっても実は変わることはない、と。唄と踊りの根源にはつねに掛合いの力が潜む。それは決して失われることはない。この掛合いの
別の言い方をしよう。掛合い的であるとは、実に肉体的な感覚に溢れ身体性に富んでいるということだ。ただただ上手く歌おう、そつなく歌おうとしているばかりで魂がこもっていない、あるいはただの自己陶酔に過ぎないといった歌い方の、まるで正反対の歌われ方がそこにある。掛合い的であることはそうした上っ面や、気取りや、はたまた自己陶酔を許さない。そこには、精神と肉体がいつも強く結ばれていてバラバラになっていない生きた人間的生命力の統一がある。その統一は、相手の唄を受け、それへの返しをまっすぐに相手に届ける想いの深さ・強さが生む統一である。掛合いは肉体となって聴き手に響かない精神なぞには退場を命じる。そのことは歌詞の内容にも見事に反映している。八月唄の歌詞は実に素朴なエロティシズムに溢れ、その表現はセクシュアルで力強い。
こうした三つの要素、掛合い、肉感性、力強いセクシュアルな表現性が一体となって実際に唄が踊りの輪のなかで歌われるならば、それは確実に参加者の意識のあり方を変える。人々を別な関係性のうちへと引き入れる。ひとりであった私が仲間の一人の私に変わる。声の震え、太鼓の振動、肉体のしなりが担う、言葉に頼る理屈によるのではない行動=身振り=演技による共感喚起的な直情的な説得力、それが漲る。
だから、奄美の八月踊りと唄は現代の私たちを強く打つ。私たちの生活に何が欠けているかを痛烈に教える力をもっている。というのも、今日の私たちの問題はひとえに《生命感の回復》をもってする《共感的絆の回復》という課題のなかにあるからだ。
しかしまた、八月踊りと唄は教えてもくれるのだ。それらの再発見される諸要素はどんなに衰弱しようと人間の生活から決して消えることはないことを。だからこそまた、人間は歌と踊りを通じてそれをあらたに蘇らせ回復することを試み続けてきたのだ、と。
奄美八月踊り唄の精神を一言に要約する歌詞はこうだ。
踊らだなすりば、島や荒れ果ててぃ
でい!
(踊らなかったなら、シマは、よ 荒れ果ててしまうぞ
さあ みんな夢中になって 踊って差上げよう、祖神に)
この一節は、かつて奄美のシマンチュ(島人)が自分のシマ(集落・島)に向けて発した言葉である。だが、それは今日の私たちに向けて発せられている奄美からの言葉だと受け取られるべきである。それは、現代の私たちが自分に引き継いで、自分自身に向けて発すべき言葉である。
ここに奄美の芸能の古代性が放つ現代性と普遍性がある。
だが、一つの大きな問題がある。
このような実に触発的な魅力をもつ八月踊りと唄の世界と私たちとのあいだには一つの障壁が置かれているのだ。つまり、八月唄で歌われている奄美方言は、そのままの形では、私たちには到底理解できないのである。この障壁を取り除くこと、つまり、歌詞の現代標準語訳がどうしても必要となる。
八月唄は、奄美が一六〇九年に薩摩島津藩の琉球侵攻の結果島津藩の統治下(
昔の奄美の人々の心はほぼ半年は八月踊りに捧げられていたといって過言ではない。四月の浜下りと虫ケラシがおこなわれ本格的な農作業の時期に入るや、心は早や稔りの八月におこなわれる豊年祭と八月踊りに飛んでいた。さまざまな準備や稽古は祭りが近づくほど頻繁となり、心はますます八月踊りに占領されていった。そして八月踊りが終われば終わったで、心はその追憶に浸った。
八月唄はその八月踊りで歌われる。八月踊りは祭りの七日七夜集落の全員の参加の下に夜明けまでおこなわれた。節や振り付けはもとより歌詞もまたすべて口伝え、見よう見まね、聞き覚えをとおして伝承されてきた。また八月唄は
こうした経緯から、その歌詞にはいまでは死語となったたいへん古い奄美の言葉がたくさんそのまま保存されている。奄美方言を知らない
かくて本書の目的がここに定まった。奄美八月踊り唄の世界を、その全貌を、誰でもが知ることができるように、上段に現代標準語訳、下段にもともとの奄美方言での歌詞を配置する対訳本を生みだすこと、これである。
しかも、本書ではこの八月踊り唄の「掛合い」性に徹底的に視点を据えて、その歌詞の紹介にあたって次のような工夫をした。
八月唄の歌詞は「八・八・八・六」の琉歌形式を取る。つまり、上の句(八・八音)と下の句(八・六音)の二節(二行詩)からなる一首が基礎単位となる。現在まで奄美大島で歌われてきた八月唄の形式では、或る一首とそれに掛合いの関係に立つ次の一首(立て返し)の計四行詩が一セットとみなされ、通常、最初の一首を男が唄い、次の立て返しの一首を女が歌うという形で歌われてきた(逆の場合もある)。
しかし、多くの研究者は、そもそもそれぞれの一首における上の句と下の句の関係自体が男と女の掛合い、つまり「相聞歌」の関係であったとみなしている。この元来の一番古い形は徳之島ではまだ残存しているとも指摘されている。事実、この視点で八月唄の歌詞を振り返れば、各一首における上の句と下の句の掛合いこそが八月唄全体の掛合い的性格の基礎中の基礎だということがわかってくる。掛合いの妙味はまずそこに萌すのである。
そこで、本書は、一応◆と○の徴で現在歌われているとおりの男女のパートの区別を示すが、同時に、そのパートの内部にあっては上の句とは下の句とが「相聞歌」の関係を結んでいることを何とか示せないものかと考えた。
たとえば、男によって一続きに下の句まで歌われる場合でも、その下の句は男の上の句に対する女からの掛合いとしても読めるよう、中性的、ないしは、むしろ女性的なニュアンスを帯びたフレーズとして訳出するよう意を用いた。だが、いうまでもなく、このことは女が上の句と下の句を一続きに唄歌う女のパートについても逆な関係においていえるだろう。すると確かに掛合いの構造はたいへん複雑なものであったということになる。
だが、そのさい奄美の言葉にはもともと男言葉・女言葉の区別がないという自在性がある。この事情がこの構造上の複雑さを人々に超えさせてくれるのかもしれない。それがあるから、実際の唄の進行のなかでは、歌い手と聴き手の双方がこの掛合いの妙味、言外の「歌諍い」(本書第二部第一章、参照)的ニュアンスをそれぞれが勝手に多様に自由に想像し楽しむことができる。歌を賭け合わせてゆくことができる。そうではないだろうか?
そこで読者には、◆と○の徴によって示される男女区別も、右のような二重性を孕むものとして味わうことをお願いしたい。
さて、次にここで声を大にして以下のことを強調しておきたい。
この対訳をつくるうえで土台となったのは、奄美大島瀬戸内町古仁屋の「古仁屋八月踊り芸能保存会」の会長を務めている富島甫が長年にわたって採集し、八月踊りの練習用にその最初の版を昭和五二年に冊子として出版した「八月踊り唄集」(平成十一年に改訂版が出された)である。大正十三年生まれの彼は今年(二〇一二年)で九十歳となるが、今でも保存会での毎週一回の練習を先頭に立って指導し、実際の公演にさいしても先導役となって全体のリズムを律する
この彼の編纂した「八月踊り唄集」と彼がその頭脳のなかに蓄え保存し続けた八月踊りと唄の節や振り、さまざまな約束事、経験、総じて奄美瀬戸内町古仁屋の諸行事、祭祀、習俗についての記憶これらなしには決して本書は誕生しなかった。彼が、どのような体験をきっかけに、どんな動機から、どういう苦労を重ねてこの歌詞の収集をおこなったか、また「古仁屋八月踊り芸能保存会」を立ち上げたか、それらのことについては本書第二部第二章「八月唄と富島甫さん」に詳しい。
なおここで八月唄の歌詞について一言しておきたい。歌詞は歌掛けの展開のなかで、踊る人々が記憶している共有された歌詞群のなかからその都度即興的に選び出され、組み合わせ直され、歌われる。そのようにして歌われた一連の歌詞が、人気を博し定着をみることももちろんある。とはいえ、その基礎はこの即興的な組み合わせの妙である。その妙・巧みさ・深い共感共振・あるいは逆に辛辣なしっぺ返し、揚げ足取り、冗談、恋愛の愁訴と陽気な遊びへの誘い、月、星、空、雲、海、木々、風、花、人生の苦と愁から心を宇宙への共感へと一転させる解放の妙、等々、これこそが「いまとここ」での生命の興奮・快楽・共振なのである。踊りと唄はそのために踊られ歌われるのだ。それは根源的に即興的であった。つまり
とはいえ、次のことは強調しておきたい。富島が採集したこの古仁屋の「八月踊り唄集」の歌詞の多様さとその物語性の深さ、掛合いや主題転換の妙、その情景描写の文学性は抜群のものである。ここではいちいち他の八月唄歌集と比較してそのことを論証することはしないが、私はそう断言しておきたい。
本書は二部構成をとる。
第一部「対訳 奄美八月踊り唄」。この第一部は、まず、対訳を理解するうえで基礎となる幾つかのことを前もって清が解説した第一章「対訳にあたって」を置き、対訳そのものは第二章に配置し、最後に、歌詞の注釈を入り口とする事項解説の第三章「八月唄を入り口に奄美の魂と民俗へ」を置く。そこでは、八月唄の歌詞と奄美の人々の信仰世界、宇宙観、習俗、奄美の自然風土、等々の事柄との密接な関連が呈示される。その解説の土台をなすのは雑誌「しまがたれ」に発表された前述の富島の記録である。その土台の上に、さらに清がこれまでの民俗学の成果をも書き加え、富島と協力して仕上げた。
また対訳は、富島が収集編纂した「八月唄集」を土台に、清が富島の協力のもとその現代標準語訳をおこなった。
第二部「八月踊り唄の世界」。この第二部は、第一章に、八月踊り唄の文化的背景を探訪する清の論考「奄美八月踊り唄探訪記」を置き、第二章に、清が富島から聞き書きし、また彼の前述の記録から引用を重ねて構成した「八月踊り唄と富島甫さん」を置く。なお、この第二章には、富島がかつての戦友斉藤春雄氏の証言をも聞き書きして、斉藤氏との連名で発表した手記「暁の戦線――沖縄弾薬輸送特攻作戦生存者の手記」からの引用も数多く含まれる。
この富島の手記「暁の戦線」について一言しておく。読者は、この奄美八月踊り唄を主題とする本に何故沖縄戦にかかわる手記が併載されるのか、と訝しく思うかもしれない。しかし、読まれるならきっと了解していただけると思う。この手記に横溢している記録への意志、民衆の一人としてどうしても書き残し、記憶にとどめ、その記憶を後に続く同胞に伝承したいという切なく、また誇り高い、富島甫の意志と類まれな情熱、これなくして、本書の土台となった古仁屋の「八月踊り唄集」もまたなかったということを。
私は思うのである。「八月踊り唄集」も、この手記「暁の戦線」も、自分は権力に属することなき、あくまでも郷土を共にする同胞民衆の一員として、その民衆たる自分たちの襟持と記憶をここに残すという意志の強烈な表明なのだ、と。
彼は私に繰り返し語った。――八月踊りと唄は決してたんなる娯楽ではない。それは祭祀であり、シマの守り神への感謝と祈願の供え物である、と。その八月踊りと唄を紹介するこの本に、あの戦争において無念の死を遂げた郷土の同胞の記憶を、彼らの鎮魂のための供え物として捧げる富島の姿を描き出すことは不可欠のことであった。
最後に、本書の「はじめに」に実にふさわしい文章であるので、平成二二年に古仁屋小学校校庭でおこなったビデオ収録「古仁屋の八月踊り」(瀬戸内ケーブルテレビ制作)に富島が「語り部」として付したナレーションを掲げる。
後の世に残そう島の宝を
語り部 富島甫
八月踊りの季節が到来して参りました。
奄美の先人たちは、昔から民俗信仰により、生活習慣のなかで稲作を特色として、太陽を崇拝し、先祖を敬い、八月踊り歌を唄って五穀豊穣と集落の安泰、家運、隆盛、無病息災を祈願して、一年の約半年は祭りの準備と七日七夜の祭りそのものをもって神への捧物としました。その祭りの主権はすべて
八月踊りはたんなる娯楽ではなく、神に捧げる神楽に等しいと言い、踊りの始めに、この歌から唄います。
盆踊りのときは、
島や
踊て
また豊年祭など他の場合では
島や
七日七夜 踊て
子供が誕生し、その祝う祝い唄としては次の唄が歌われました。
親ぬ後継ぎや
昔は踊る広場の真ん中に焚き火をして踊りの輪が大きくなり、踊りの場に収まらないと、二重の輪をつくり、酒や食べ物がふるまわれました。島の盆踊りの良さは、老若男女、他国の人、地元の人の区別なく、貧富の差もなく、和気あいあいの仲で唄い踊ったことにあります。「踊らだなすりば、島や荒れ果ててぃ
この貴重な文化遺産である八月踊りの収録が、この遺産が次の世代に継承されるためにお役に立つことができますならば、幸いです。昔を今に、根強く伝統され、先祖が残してくださいました素晴らしい八月踊りが、いっそう盛んに踊られますよう、皆様と共に願っております。

![]() 2013年以降
2013年以降
順番は古い順になっています。
リンク 私という書庫
