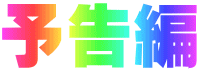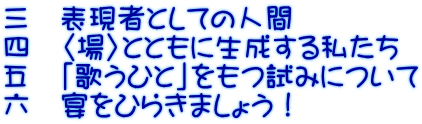
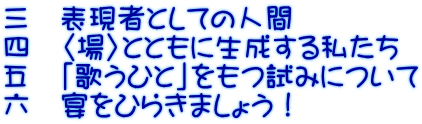

――友人たちへの提案
一つ提案があります。アイデアがひらめいたのです。
小さな展覧会をやろうという提案です。誰の展覧会ですって?
もちろん、ぼくたちのですよ。
どこでやるんだとおっしゃるんですか?
誰かの家で、誰かのガレージで、アパートの空き部屋、会社の倉庫の角、なじみの喫茶店で。小さなスナックを一日だけ借り切って。どこかあるはずです。「友遠の友達は友達」、これを合い言葉につてをたどって探しだす気さえあればね。
まあ、聞いてください。
ぼくのアイデアを。突然ぼくのなかにひらめいた一つの「生きる技術」、〈場〉のイメージを。ぼくらの間柄についてのぼくのヴィジョン。生活へのヴィジョンを。
![]()
「ああ、また君の夢想か」などといわないでください。
ちょっとした裏づけというものがあるんですよ。まるっきりの絵空事、綿菓子のような夢物語とは大ちがい。<生活>のヴィジョンなんです。「暮らしの技術」なんです。
実際にぼくは去年、この「ミニ展覧会}というものを経験したんですよ。
だからまず、その経験についてしゃべらせてください!
話はひょんなことで生まれました。小さな読書サークルがありました。いや、いまもあるんですが。もともとは、「民芸」という一つの美の思想を生みだした柳宗悦という思想家の本を読む目的で出発した小さなサークルでした。
「柳宗悦って誰か?」ですって。このさいそれは脇に置きましょう。
とにかく、そのうち、月に一度のこの読書会が終わった後のお酒を入れたおしゃべりが楽しくて、読書会なのか、それを口実にした飲み会なのか、わからなくなってしまったような集まりとなったのです。
最長老は八十三歳のご老人。最年少は、大学を出たばかりの若いお嬢さん。主力は、四十代後半の男性と女性。男と女の人数はちょうど半々ぐらい。職業は実にさまざま。会のメンバー全体で十数人の集まり。
そのなかのぼくとY氏とのあいだに、あることがきっかけで、水彩絵の具で庭や花瓶の草花を葉書に一輪写生して自家製の絵葉書をつくり、それを送りあうということが始まっていました。
また、ぼくやK氏やS氏は以前から素人写真に凝っていて、この読書会の例会にときどきお互いの作品を待ち寄っては見せあっていました。またこの読書会の昔からの世話人で、美術館の学芸員も勤めたことがあり、読書会の会場にいつも彼女の一人住まいのマンションの大きなリビングを使わせてくれるTさんは、以前から版画をつくる趣味をもっていました。
そんななかである日、この四、五人の人間のあいだで、お互いの最近の作品を持ち寄っての「ミニ展覧会」を、Tさんのマンションを会場にしてほんの一日ひらこうではないかというアイデアが浮かんだのです。
そうです。暮らしをほんのちょっと弾ませるための小さな思いつきだったんです。
ところが、このアイデアは話し今っているうちにまるでパン種のように膨らみだしたのです。読書会のメンバー全員がなんらかの形で参加する、会全体のおこなうお楽しみの企画へと発展したのです。
というのも、そのときぼくたちのなかで育ちつつあった「ミニ展覧会」というヴィジョンの眼で会のメンバーを見わたしてみれば、誰もが何かを持ち寄ることができるはずのひとびとだったのです。
ミニ展覧会のイメージが確立しました。一つのヴィジョンが誕生したのです!
手のすいているひとたちで土曜の午前中に会場の飾りつけや展示をおこなう。土曜の午後から日曜のお昼までを展覧会とする。その土曜の夜はもちろん飲み会。「展覧会祝賀パーティー」と銘打って。しかし、展示物を飾り付けた会場でやるのだから料理はできるだけ簡単なものにして、後片づけの手間がいらないやり方で。
Mさんが彼女の家庭菜園からとれたてのじゃがいもを持参して、茄でたてのじゃがいもにベーコンとバター、そしてビールの、ビールパーティーを基本とすると決まりました。
会のメンバー全員に手紙で構想が伝えられました。
三ヵ月後の開催の日時と、それまでにできるだけたくさんの会員がなにか展覧会に待ち寄る自分の「作品」を考え、つくりだそうというアピールがなされました。
![]()
三ヶ月後の当日、どんなものがマンションの一室を飾ったでしょうか?
仲よく並べられた、互いの手元にある相手のくれた二十通近くの交換絵葉書を貼りつけたアルバムニ冊。三人の写真愛好者からは、写真パネル二点、自称「傑作写真」を集めたアルバム数冊、そこから希望者にお分けしますとつくりだされた数種類のポストカード二十数枚。お気に入りの六文字の言葉だけをくりかえし練習した数十枚の半紙を一冊に綴じてつくった「私の手習い帳」一冊。親子でつくった絵本三冊。額に入れた版画数点と、それをポストカードとして刷ったもの。水彩画教室へ通って最近描いた絵一点。
実際にプロの作家として織りと染めをやっている二人の会員からは、作品の帯地と生地をそれぞれ二点。
籠に盛られた家庭菜園でとれた野菜たち。菜園の四季と作物を記録したアルバム、作業日誌や作付けの計画書。そして、野菜や庭の草花を葉書大の和紙に淡彩したもの。
自宅の庭の草花を生けた活け花。昨年ネパールヘ一月ほどの旅をしたとき購入した数十種類のネパール紙の束、等々。
「展覧会」といいました。
いまぼくはあらためて考えています。あなたにこの提案の文章を書きながら。あの「ミニ展覧会」とはどういう〈場〉であったのだろうか、また、どういう<場>となる可能性を宿していたのか? と。
こうあらためて問いましょう。それはどんな「展覧会」であったのか? と。
もちろん、ぼくたちが、いま紹介したような物を、まずお互いに向けて展示しようとした「展覧会」でした。
では、さらに問いましょう。その「ぼくたち」とは誰であるのか? そのような物とはどんな物なのか?「お互いに向けて」とは誰に向けてのことか?
展示された物は、たとえそれがどんなに拙劣な物であったとしても、ぼくたちのかけがえのない「作品」でした。つまり、表現体でした。
表現体とはいかなる物でしょうか。
そこでは二つのものが切り離しがたい結びつきをもって表現されていました。
そこに表現されていたものは、まずそれが直接に表していた物です。描かれた草花、撮られた風景や人間、書かれた字、つくられた作物、織られた布、染められた糸、生けられた花、持ち込まれた紙、等々。
とはいえ、同時にそれは、それをそのように描き、撮影し、書き、つくり、織り、生け、買い求め運んだ人間の感受性や欲望、イメージや憧れ、経験や記億をその物につき従う影のような形で同時に表現していました。
「あっ、このひとはこういう物が奸きなひとなんだ!」という発見が展示の場には同時につねに誕生していたのでした。たとえば、S氏は兄さんの家庭菜園に出かけ野菜たちの写真を撮って作品として展示しました。
風に揺れるネギ坊主、苗床の脇に咲く小さな薄紫の花、畑脇の土中に埋めた泥バケツのなかの蓮のつぼみ、キャベツの柴の葉脈が描くアブストラクトのさまざまなバリエーション、そうしたものを彼は開放シャッターで接写したのでした。それは、もの静かでいささか地味すぎると思われるほどのS氏の日頃の風貌からは想像もつかない、生きいきとした可愛らしさにあふれた写真でした。そこには少女の感情がそよいでいるとさえ思えたほどでした。
先ほどぼくはこう問いました。展示していたのはまぎれもなく「ぼくたち」であったが、さらにいってその「ぼくたち」とは誰であるのか、と。
展覧会で印象的な作品がぼくたちの眼をとらえるとき、ぼくたちは思わずこう声をあげます。「これをつくったのは誰なんだ!」と。
たしかにぼくたちの「ミニ展覧会」では全員が知り合いです。
たしかに即座に答が返ってくるでしょう。「それをつくったのは彼です。彼女です」。
しかし、実のところ、それは求められた答でしょうか?
「それをつくったのは彼です、彼女です」とぼくたちが答えたとしても、問いはさらにぼくたちを追っかけてこう問うのではないでしょうか。
「では、彼とは誰であるか?」と。「こういう物が好きな彼は、彼女は、誰であるのか?」と。この風に揺れるネギ坊主を撮ったS氏とはいったい誰であるのか、と。
展示されているのは、物であると同時にそのひとでした。
そして展示されている「そのひと」は、これまでぼくたちが知っていると思い込んでいた「そのひと」からはうかがいしれなかった「そのひと」、「そのひと」が「そのひと」 であったぼくたちにとって、「そのひと」の輪郭からあふれだしてしまう「そのひと」でした。
そして、もしかしたら「そのひと」は、「そのひと」白身が理解する「そのひと」もどこかで超え出てしまう「そのひと」なのかもしれません。

――架空三人問答
これはぼくが創作した架空の三人問答である。とはいえこの創作はぼくが経験した幾つかの実際の対話を下敷きにしている。登場人物の一人ゾンは一九七〇年前後に学生であった人間を、またクーは今学生である男を、またジジも同じぐらいの年の女を想定している。
オンブオバケ
ジジ:クー、あんたはどんなオンブオバケを背負ってきた?
クー:えっ、オンブオバケって何さ?
ジジ:ゾンさんも聞いて! 昨日、何気にテレビ見てた。『マンガ昔話』、ほら、子供の頃よく見てたやつの再放送。するとオンブオバケってのが出てきたんよ。暗い山道を与作が歩いてると、ひょいとオンブオバケが与作の背中にとりつく。与作は最初は気がつかないんやわ。でも、なんだか体が重くなってきて、へんに山道がこたえてきて、ぜぇぜぇぜぇぜぇ息が切れるようになってくる。お月さんが出てきて、ふと与作が自分の影を見ると、影が二重になってるようで変なんやわ。自分の背中に何かがおぶさってるようで、「あれっ?」て振り返るけど、ちらっと影が見えても、なにしろ背中におぶさってるオバケやからよう見えん。で、与作は振り払おうと、急に駆け出したり、ジャンプしたり、転がったりするけど、そうすればそうするほど、なんだかますますしっかり重くオバケにしがみつかれたみたいになる。
クー:それ、俺も見たことある。で、嫁が与作の帰りが遅いんで提灯もって迎えに出て、大声でいうんや。「与作どん、オンブオバケがついとりますらぁー。与作どん、オンブオバケがついとりますらぁー。消えてくれろー。与作どんのオンブオバケさんよ! 消えてくれろー」って。
ジジ:そうそう。でね、うち、このオンブオバケって《自分》って問題やないかって、閃いた。ゾンさん、そやない?
ゾン:冴えてるね。そのオンブオバケってメタファーは《自分》って問題を考えるのにぴったりかもしれんよ。
ジジ:メタファーって?
ゾン:あっ、比喩ってこと。つまりイメージによる比喩。オンブオバケにとりつかれた与作というイメージを見て、それは《自分》って問題の姿と似てると思ったら、そのイメージは《自分》という存在のメタファーになっているというわけさ。《自分》っていう問題を、それを象徴するイメージをあれこれつなげて、そのつながりで考えていくこともできる。
クー:イメージ思考って面白い。俺、フロイトとかユングとか精神分析学の本ちょっと齧ってるんだけど、そこでは強調されてた。夢を通じても人間は実は思考してるんだけど、夢ってのはイメージだから、それはイメージによる思考、そして文学では詩が典型的にイメージ思考で、絵もそう。夢と詩と絵は一直線につながっているところがあって、それは或る事を多義的な仕方で思考するのには都合がいいというか、多義的に思考するためにはそれしかないっていうか、思考するうえでのそういう意義があるんだって。つまり或る物事が一つの意味しかもたないのではなくて、複数の意味を同時にもったり、メダルの表と裏の関係でポジティヴィヴな意味とネガティヴな意味とがくっついていて、突然表が裏にひっくりかえるとか、その逆とか、そういう動きのなかで物事を捉えようとするときに重要になるってさ。それは直観的思考でもあって、多義的でありながら同時にそこに統一があるような全体像を頭にいつも残しておくためには絶対に必要だって。
論理一本やりで思考してゆくのは一義的思考で、それは概念や定義をつねに厳密にしていって、それで曖昧さを排除して論理を矛盾なく明晰に通していくんだけど、或る物事をほんとうに思考するためには、論理的思考力とイメージ的思考力と両方が必要だって、その本は強調していた。で?
ジジ:うちの家族ちょっと変わってんのや。
クー:でも、たいがい人間って、実は心のなかでは自分のことや自分の家族のことちょっと変わってるって考えてるんじゃない? でも、思いっきり変わったのに出会うと、ああ、俺らは「普通だ」って思うのも事実だけど。
ジジ:そうそう。「変わってる」って思ったら「フツウ」が気になって、「フツウ」と思うと「変わってる」のが気になる。そのことも《自分》って問題そのものやなぁー。でな、うちがちょっと変わってると思ったのは、うちの両親は結婚してすぐにアメリカに渡って、それは、このまま日本におっても人生に飛躍を起こせへんって考えたからなんやけど、五年間暮らして、英語をすっかり身につけて、日本に帰って父は大学の先生の端っこに潜り込んで、母は塾の講師になって、両方とも英語の教師になった人なんやわ。うち姉が一人おるん。姉は両親の血継いでほんまに英語好きで得意なんや。
今になってわかるんよ。うちの一家の物の考え方、生活スタイル、いろいろな嗜好、どっかアメリカ風なんや。そやから、うちも小さいころから周りとちょっといつもずれてたと思う。それ、幼稚園に進んではっきり気づいた。うちが「フツウ」って思ってたことは「フツウ」やなくて、変わってたんや、って。
ゾン:そのあたりから《自分》って問題が始まりだす。幼稚園は「社会」っていう《他者》との最初の出会いだろうね、一般的にいうと。《他者》って存在にぶつかって、それに跳ね返されるようにして《自分》って存在が生まれる。《他者》ってなんか気取った硬い言い方をここでわざとしたのは、「すごく自分と違う、別や!」っていう意識がしっかり貼りついた存在に相手がなって、そういう存在として自分に関係してくるという点を強調したいからなんだけど。変な言い方かもしれんが、まだ《他者》でなかった相手が《他者》になるから、自分のほうは《自分》になるってことさ。
《他者》が生まれることで《自己》が生まれる
クー:ジジがいった経験は家族の外に《他者》がいたことを発見したという経験だけど、自分の家族が実は《他者》だった!って発見もあるんじゃない、ゾン? あるとき母が話してくれたんだけど、おもしろかった。母は小学校三年ぐらいのときかな、自分も含めて物が全部風船のように浮かび上がって、全部地上から宇宙にゆらゆら泳ぎだしていってしまうんじゃないかと恐怖にとらわれたんだって。誰にもいえない秘密の恐怖感。寝るときはいつもその恐怖がはっきり意識にやってきて、なかなか寝付かれなかった。ある日理科の時間に先生が引力ってことを授業でやって、「みんな、だから地上の物は宇宙に飛んでいかないんだよ、安心だね」とかなんとか教えてくれたらしい。で、母は「助かった!」って心のなかで大声あげて、学校終わったら、全力疾走で家に帰って、母の母に、つまり俺のばあちゃん、ばあちゃんに「おかあちゃん! おかあちゃん! 助かった! 引力ってものがあって、宇宙に飛んでいかなくていいんだって!」と玄関開けたとたんに叫んだ。
というのは、母は当然ばあちゃんも自分と同じに毎晩恐怖でおちおち寝れなかったにちがいないと思いこんでいて、だから誰よりも先にこのことばあちゃんに伝えてばあちゃんを安心させたかったんだ。いちばん自分と一緒に喜んでくれると思ってさ。ところが、ばあちゃんは大笑いさ。「馬鹿ねぇ、あんた、そんなこと悩んでたの? あんた馬鹿ねぇ!」って。母はそれが悲しかったって。それでその後三日、時々思い出しては泣いたって。自分と自分の「おかあちゃん」が全然別の人間で自分がいちばん悩んでいたことが彼女の悩みでは全然なくて、二人は全然別の世界にいたことがわかって、それが悲しくて仕方なかったって。
ゾンさんの言い方借りれば、そのとき母にとってばあちゃんが《他者》になったってことだね、そして、それがきっかけで母は《自分》になったってことだ。
ゾン:クー。それはいい話だね。人生を感じさせるいい話だ。そのとおり、クー。家族の外にいる「社会」という《他者》に出会うころ、家族は時を同じくして《他者》に変わり、その二重性のなかで自分は《自分》になる。たぶんそうじゃないかな。で、ジジ、それとオンブオバケってテーマはどうつながる?
ジジ:二つのことがあったと思う。「着色」ということと「居場所探し」ということと。うちが「みんなはフツウで、うちは変わってる」って意識したのは、いろんなことを通じて、「あんた変わってるわ、生意気や、自慢しいや」ってゆう風にうちの無意識のアメリカ流がみんなに嫌われていることに気づいたことによるんやけど、そんとき、うちは「真っ白な自分」がうちのことを特徴づけるそういったいろんな言葉でまわりから色を塗られたという風に感じた。そんことをよく覚えてる。みんなのうちを見る視線によってうちが着色されてゆくってことやね。それが「着色」ってこと。この着色は言葉による着色。どうゆったらええかな。原色のペンキでべたに塗られるって感じかな。「変わってる」は赤で、「生意気」は青で、「自慢しい」は黒って感じ。そういう言葉でべたに塗られるって感じ。
さっきクーがイメージ思考のことを多義性ってゆうことで特徴づけて、一義性と対比したけど、この場合はちょうど反対みたいな感じ。多義性が全部消されて、「変わってる」の一言でべたに一義的な赤ペンキがうちに塗られるって感じ。言葉による着色はそういうべたなペンキ塗りしかできへんって感じ。
ゾン:「居場所探し」ってのは?
ジジ:ほら、うちの場合はそういうわけでまずネガティヴな着色がきたわけやろ。で、その排除のベクトルに怯えて、これはやばい、このままやったら、うちの居場所あらへんわ、どうやったら居場所を確保できるんやろ? って意識が動き出してくる。もっとも、それははっきりした形では小学校高学年ぐらいからかな。出発点は幼稚園の「着色」経験だけど、幼稚園から小学校の低学年ぐらいまでは、まだ子供はそれでも社会化されきれてない面があって、てんで勝手にリスやネズミの小動物みたく動いてる面ある。そやない?
でも高学年になるとみんなクラスの人間関係をはっきり権力関係で捉えるようになりだすやん! 誰が強くて誰が弱い、誰がイケテて誰がイケテないか、誰がどのグループで、そのリーダーは誰で、自分は力のヒエラルキーのなかのどこにおるかってことが、学校での暮らしの最大のテーマに競りあがってくるやろ?
今から振り返ったら、「しょうもなっ!」って思うわ、うちだいぶ強くなったからね。でもそのときは確かに「取り入ろう」って意識が働いたんよ。一言でいうと、「変わってる」のはやばい、「フツウ」にならなくちゃってゆう意識。それから、うちの場合は「明るい子」にならなくちゃってのもすごくあった。というのは、そんな風に自分の意識からゆえば突然にネガティヴに着色されたわけだから、当然わけがわかんなくて暗くもなるやん。なんかおどおどするし、それに、自分にこだわって、「うちは頑固にうちで一人でいることのほうが好き」って居直って振舞ってると、それも「暗い」って見られてることがよくわかったから。今でもそやと思うけど、「暗い」って言葉は「ひとりである」・「ひとりでいる」ってことと同じ意味で使われておる気がする。そして頭ごなしに、そのことが悪いこととされていると思う。
今でもはっきり覚えていて、自分のなかで「ショートカット事件」って呼んでるんやけど、こんなことがあった。
クラスにMちゃんという女子からも男子からも好かれる女の子がおったんよ。うちMちゃん見てて、猛烈にこの子みたくなりたいって思った。自分を変えたい、Mちゃんみたくなりたい、で、その第一の手立ては髪を切ることやった。そのころうちは長い長い髪をしてた。それにそれは心の中の自慢やった。うちはそれが好きやったんや。でも、Mちゃんのようにショートヘアーにしようとばっさり切った。あんなに好きな長い髪を、や。そやけど、それをばっさり切ったら、ほんまに自分が変わったって気がした。つまり「キャラ変更」やね。ほんま路線転換やわ。
ちょっとうちも極端やからね。突然「明るい元気な子」になっちゃった。でも、このキャラ変更は同時に「明るい子オンブオバケ」を背負うことでもあった。そう思うんや。てゆうのは、人に好かれるために、いじめられないように“明るく元気であれ!”というこのオンブオバケを背負ってからのうちの豹変ぶりは凄まじかったと、今も思い出せるから。うちは必要以上に愉快さを追求した。アメリカ風の家のことや弱々しそうなイメージでいじめられるんだとしたら、それに負けないぐらい“おもろいやつ”にならなければと努めた。家のことも話さなくなった。そのかわりにみんなに合わして、完璧「受け狙い」に入った。その試みは成功したかに見えた。実際それから除けもんにされることはなくなったし、まわりりはすっかり信じ込んだもん、ジジは「おもろいキャラ」なんや、と。
でも、ほんまは自分で自分に納得がいかんかった。
クー:詐欺師はまず自分を詐欺らにゃならん、自分に信じ込ませてこそまわりを信じ込ませることができるって、誰かがいってたぜ。
ジジ:そうそう、そうゆう感じ。うち、自分に自分が詐欺られとるんとちがう? って気がしだした。まわりが「おもろいジジ」を信じ込むにつれて、だんだん。それに、いったん悪に手を染めると肘までってゆうやん! 「ショートカット事件」は尾を引いたわ。結構それは大成功だったから余計に。つまりキャラ変更のこつを知ったってゆうか。味を知ったってゆうか。できるようになっちゃったってゆうか。
ゾン:ナイーヴな純朴なジジをどっかに置き去りにしてかい?
ジジ:そや! うちは意地悪な性分になって、英語的にいうと、それだけ「スマート」になった。大阪弁でいうと「ボケ」やなくなった。最悪なのは中学時代や。「おもろいジジ」のマスクの下には実はあらゆるコンプレックスの固まりのうちがおった。とゆうか、そういう固まりに中学時代とともになっていった。
いつしか気がついたら、うちは「おもろいジジ」とゆう戦略より「フツウの子」戦略に転換していた。「おもろいジジ」はほんま気の許せる相手にしかとらなくなった。それはうちが仲間の数人のグループに守られるための内堀用で、外堀は「フツウの子」戦略。中学時代は誰もがそやとは思うけどな。コンプレックスの固まり。うちがそうなったのは、うちがクラスと家との挟み撃ちにあってたからやと思う。つまり、どっちの世界でもうちは脅かされていた。比較という罠に。クラスではいつも自分をほかの誰彼と心の中で比較して喜んだり悲しんだり憎んだりしてた。家ではまず姉とうちを比較して、いつもコンプレックスの罠に落ち込んだ。
クー:罠って?
ジジ:「罠」ってゆったんは「ハメラレタ」ってこと。そこに「ハメラレタ」ら、うちのエネルギーが全部吸収されていってしまうやん。お姉ちゃんみたいになれるか、それともなれへんかという問題だけに。つまり、その問題が中心軸になって、すべてが回転しだすことになっちまうやん。「これがあんたの立つ土俵よ」、って。ほんまは、「うちそんな土俵に立つ気あらへん、うちの立つ土俵はもっと全然別な土俵なんや、さいなら!」ってゆうべきなのに、それがいえへんようになってしまう、そんこと。
それにこうゆうこともあったんよ。心の中でいつも自分と他の子を比較してたから、比較されるのが怖かった。比較されないためのいちばん安全地帯は「フツウの子」になることやと思った。これ、うちの中学時代の生きる戦略やね。
クー:おまえ頭いいじゃねえか。
ジジ:ゆったやないの。うちはスマートやったって。うちは自分に言い聞かした。「自分はこんなもんだ、これ以上、上を目指す必要はない。人気があったりモテる子は自分とはちがう上流な人なんや。そやから、うらやましがってはいかん。自分は良い意味でも悪い意味でも逸脱したくない、『フツウの子』でいられたらええんや」って。
ゾンさん、「フツウの子」でいるためには目には見えないさまざまな項目をパスしなければならないんよ。「女の子として人一倍清潔であれ」ってことは「シャンプーの匂いは必須!」ってことで、「体力をつけろ」ってことは何故かというと、「運動会では大活躍しなくとも失敗するな!」ってことで、「好きな人は必ず作る」ということは、クラスの仲間との会話で「バレンタインや恋占いの話題になったときついていくためには必須」ってこと。「フツウ」ってことは、「あんたは特別可愛くなくてもええんよ」って自分への慰めであると同時に、「あんたは絶対ブスであってはだめ!」ってことでもあるんよ。つまり比較されることからのダメージを最小限にとどめよ!ってことやね。
そやから、うちは、「フツウ」の範囲で友達を選んだり、おしゃれをしたり、人を好きになったりした。先輩にも従順でさからわず、絶対に目をつけられたくないといつも思っていたし、上と比較せず自分より悲惨な状況の子、自分より「イケテナイ子」たち、つまり「下の子」と比較することで嫌な経験、辛い経験をすることから逃げてた。そういう卑怯者にだんだんなっていった。でも、それが自分でも納得ゆかんかった。自分は性悪の嫌な奴になり下がってんのとちがう? その気持ちは消しがたかった。
 ――ある若い友人にあてた手紙
――ある若い友人にあてた手紙
お元気ですか。
もうまもなく入社式があり、君もいよいよ社会人ですね。
その社会人としての第一歩を踏み出そうとしている君のことを考えていて、ふと、話してみたいことが生まれました。それでこうして手紙を書いています。
それがはたして君の社会人としての門出にふさわしい話題となるのかどうか、僕にはわかりません。でもそれは、君の門出を祝いたいという僕の想いと一つになったものとして、僕のなかに浮かび上がってきたことなのです。
一 小さな美しいものをつくる
君に話してみたいのは、〈つくる〉という経験についてです。
いきなりこういうと、君はとまどうことでしょう。
君はパンをつくる会社に入社したそうですね。〈つくる〉というのはそれこそパンをつくる、野菜や米をつくる、自動車をつくる、ビルをつくる、あるいはまたプラモデルをつくる、人形をつくる。セーターを編む、手作りの絵葉書をつくる、大きなものから小さなものまで、職業に直結しているものから趣味と呼ばれる領域のものまで、実にさまざまあるわけですが、いまここで僕が君に話してみたい問題というのはちょっと抽象的にいうとこんなことです。
――なにかある小さな美しいものを自分の手で丹精をこめてつくりだす、そういう手作りの世界を自分の暮らしのなかにもつという問題。そしてその自分の小さな「作品」をなかだちにして自分と自分の親しいひとたち、家族や友人たちがあらためてお互いを結びあうという問題。つくり、そして贈る、与えるということ、それが小さな美しいものの手作りということにかかわって生じる、そういう時間なり空問、あるいは関係というものを自分の暮らしのなかにかけがえのない大切なものとしてもつということ、そのことの意味についてあらためて考えてみたいということなのです。
いま僕は、「小さな美しいもの」といいました。小さいといったのは、別に特別な芸術的な才能や職人としての修行を積んだわけではない普通の僕たちであってもみずからつくりだせるもの、という意味をこめてのことです。小さな手作りの世界を思い浮かべてみてください。そして、いま自分はどんな小さな手作りの世界を自分の世界としてもっているかなと、自分に問いかけてみてくれませんか。小学校の頃の図画工作の時間、プラモデルの世界や手芸の世界、日曜大工の世界、園芸の世界、そしてまた料理やお菓子作りの世界、そういう世界と自分とのつきあい方がいまどうなっているか。君の場合はどうでしょうか。
実は僕は、後で話す最近のある経験がきっかけとかって、いかに長らく自分かそうした手作りの世界と縁が切れた暮らしを送ってきたかということを痛感することがあったのです。
美しいものといいましたね。そのことで僕が考えているのは、手作りの世界はおのずと美しいものを追求しだすという、つくることと美しさの追求との切っても切れない関係なのです。強制されていやいやつくるときは、僕たちは美しさなど気にかけず、とにかく早くこの仕事を片づけてしまいたいとそのことばかり考えますが、自分で手作りの世界にのりだしたときは、僕たちは誰にいわれたわけでもないのに自分でできるかぎり美しいものをつくろうと一所懸命になります。そうではないでしょうか。なにも芸術家や特別の芸術愛好家・趣味人ではなくとも、普通の僕たちの暮らしのなかにも美への要求が自然に備わり湧き出し成長する世界があるということです。もし、僕たちが自分の暮らしのなかに自分の好きでならない手作りの世界をもつならば、美しいものへの感受性や欲求がそこから力強く湧か出し育ってくる一つの源泉を自分のかかにもつことになるのではないでしょうか。
ところで、そもそもなぜこんな手作りの世界についての話を僕は君にしだしたのでしょうか?
実はそこにはある特別な理由が、最近の僕の個人的な経験に根ざす特別な理由があるのです。
二 入院という〈経験〉をとおして
たぶん君も少し聞いていたと思いますが、実は僕は去年の夏から暮れまでほぼ五ヵ月入院生活をおくりました。実際、五ヵ月という期間はけっして短い時間ではありませんし、またそれだけの入院を要したわけですから僕の病気も軽いものというわけではなかったのですが……。そういうわけで、僕としてもいろいろと考えることがありました。考えざるをえない日々でした。
とはいえ、たしかに僕の病気は軽いものではありませんでしたが、だからといってもう気息えんえん、ベッドに倒れ伏して何もすることができないというわけではありませんでした。病気によっても、病状によっても、入院生活も実はたいへんさまざまです。さまざまな段階があります。すでに病の峠を越して体の回復を待っている患者もいれば、入院して病名がつきとめられ治療方針が決まるまで長い検査の期間を待たねばならない患者もいます。そして僕の見るところ、かなり多くの患者は病院の外に出て普通の仕事につくだけの力はもちろんないにしろ、だから入院しているわけですが、病室のなかで、あるいはベッドの上で本を読んだり、手紙を書いたり、ちょっとした絵を描いたり、手芸をしたり、工作をしたりする体力は十分にもっていたのです。もっているはずなのです。
しかし、この点で僕が強烈な印象を抱いたのは、実は病室のほとんどの患者たちが、青年も中年も老人も例外なく、朝起きてから夜寝るまで、昼間ベッドの上でうとうとしているとき以外はほんとうに一日じゅうといっていいほど、テレビを見て過ごしているということだったのです。それぞれのベッドの脇には個人専用の小さなテレビが設置されていて、それをイヤホンで聴さながら見るのですが、それしか他にすることはないといって過言でないほどに患者たちがテレビを見て一日を暮らしている姿に、僕は強烈な印象をもったのです。
君はまもなく社会人としてのスタートを切るのだなとぼんやり考えているうちに、ふと、僕はそのときの強烈な印象について思い出したというわけです。それがもしかしたら、この手紙を君に古くきっかけになったのかもしれません。
いうまでもなく、入院することによってひとは否応なくそのひとがそれまで携わってきた仕事や社会的な活動から切り離されます。切り離されるということは、なによりも膨大な時間がそれまでその使用のために定められていた使用目的を失って、自分のもとにいわば逆流してくるということです。使い途が定められていたはずの時問が突然、使い途が定められていない時問に変身して、自分のもとに逆流してくるわけです。
さて、問題はこの時間の変身にぶつかって人院患者の僕たちはどうすることになったのか、時問は使い途のわからない時問となって大きなとまどいと混乱のなかで自分のもとに逆流してくるのでしょうか。それとも、これまでの定められた使い途から外され、いわば解放されることで、別な使い途が可能となったものとして、別な使い途を新しく発案することができるものとして、積極的に迎えられるのでしょうか。
ところで入院という状況は、本質的に人間にあらためて自己と向きあうことを大なり小なり要求するものとして僕たちに追ってくるものだといえるはずです。まず自分の病気への大きな不安があるはずでしょうし、幸いなことにたとえそれがあまり不安をもたらさないものであっても、同室の患者の抱える事情や病院内のさまざまな出来事、医師や看護婦とのさまざまな会話が根本的には僕たちにあらためて人間の生き死にの問題を考えざるをえないものとして迫ってきます。そして入院中は僕たちは基本的に独りなのです。家族からの毎日の面会があったとしても、一緒に過ごすのはせいぜい一時間ほどのことでしかないでしょう。そして病院内で取り結ばれる人間関係はもちろん例外はあるにせよ、ごくごく表面的なものです。誰もが一日も早く退院することを望み、ここにいることはほんの一時のことと考えようとするからです。「袖触れ合うも多生の縁」といいますが、要するに「袖触れ合う」程度の関係でしかないとお互いに考えるわけでしょう。僕たちは基本的に独りなのです。
この独りであることをどう生きるかという問題が患者には生じてきます。そしてこの点で僕には次のことが重要な点だと思われたんです。それはどういうことかというと、根本的に独りであるということには必ず相異なる二つの面が分かちがたく絡みあって存在するのだということです。そこには、独りにさせられたという悲しい面とともに、実は独りになれたというある種の解放を伴う面が存在するように、僕には思われたのです。そうではないでしょうか。
現代生活はあまりにも忙しくかつ関係が密に織りなされているので、僕たちには「孤独になる自由」すら許されていないといわざるをえない面があるのではないでしょうか。たんに仕事の場だけでなく、家族という場においても僕たちはさまざまな役割を期待され、期待されるという形で押しつけられ、しかもそれを心の内側にまで取り込んでしまって、がんじがらめにされているという面があるわけでしょう。入院は、一時であれその人間関係を断ち切ってくれます。僕たちが僕たちの負った役割を期待どおりに果たすことを露骨に期待し要求する相手の顔、眼差し、[それを見てしまえば、逃げられないな]と感じさせるこの人間の顔や眼のもつ力というものから、僕たちは一時であれ解放される、そのことであらためて自分と向きあうことが可能になるチャンスを得る、そういう問題の側面がそこには必ず含まれていると思われるのです。喜ばしき解放とまではけっしていえないのですが、ある種の解放の面がそこにはあるはずなのです。入院という悲しく辛い現実のなかにも。
そして、一時のこととはいえ、入院を要するほどの治療ということになればたいてい一ヶ月ぐらいの入院生活は最低限度覚悟しなければならなくなるのです。一時のことといっても、それは多くのひとにとってはけっして短くはない、相当の量の時間を意味するはずなのです。
さて、先ほどいいましたね。僕にたいへん強烈な印象を与えたのは、ほとんどの患者が一日をひたすらテレビを見て過ごしていることであったと。
君にはそのことはどう感じられるでしょうか。
僕にはその光景は実に寂しく貧しい光景として感じられたのですが。
はたして、入院によって自分のもとにそれまでの定められた使い途から外されたものとして逆流してきた時間は、そのままテレビに流し込まれてしまってよい時間なのでしょうか。「ああ、僕たちは時間を吸いとられっぱなしなんだ?」と、そのとき僕は感じました。自分の時間の使い途をあまりに他人によって決められてきたおかけで、あるいは他人任せにしてきたおかげで、その他人からの指定が解除されるや、僕たちは途端に時間の使い途がわからなくなって今度はテレビにそれをゆだねてしまうのではないのか、そう直観的に感じられました。
そのとき同時に僕をとらえたのは、「では、ここにないもの、欠けているもの、不在のものとは何だろうか?」という問いでした。目覚めている時間の大半を、イヤホーンを耳にテレビに独り向きあってたいして面白くもなさそうに画面をぼんやり見て暮らすという、この病室を貧しいものと感じたとすれば、それは何がそこにないから、何がそこに不在だからなのか、それが僕の問いとなりました。
君に話してみたくなったのはこの問題なのです。