

![]()
 ――ドストエフスキーから
――ドストエフスキーから
アリョーシャ:みなさん、わたしはここで、……この場で、みなさんにちょっと言っておきたいことがあります!
かわいいみなさん。みなさんにはわたしの言うことはわからないかもしれません。わたしはときどきたいへんわかりにくいことを言うから。
しかし、それでもみなさんはいつかわたしの言葉を思い出して、納得されることがありましょう。何でも楽しい日の思い出ほど、ことに子供の時分、親のひざもとで暮らした日の思い出ほど、その後の一生涯にとって尊く力強い、健全で有益なものはありません。みなさんは教育ということについていろいろやかましい話を聞くでしょう。けれど、子供のときから保存されている、こうした美しい神聖な思い出こそ、何よりもいちばんよい教育なのかもしれません。
コロス(男女):そんなふうにカラマーゾフの三兄弟の末の弟アリョーシャはイリューシャの埋葬の日、イリューシャのクラスの子供たちに語りかけたという。
アリョーシャ:過去にそういう追憶をたくさんあつめたものは、一生救われるのです。もしそういうものが一つでも、わたしたちの心に残っておれば、その思い出はいつかわたしたちを救うでしょう。
コロス(女):アリョーシャ! アリョーシャ! アリョーシャ!
それは本当なの?
それは本当なの?
Ⅱ
コロス(男):おかしな男がいた。そいつは自殺しようと決心したそうだ。二ヶ月前に素敵なピストルを買い込んだそうだ。
おかしな男:通りで……ふと空を仰いだ。空は恐ろしく暗かった。だが、ちぎれ雲のあいだあいだに底のない真っ暗な斑点をまざまざと見分けることができた。とつぜん、俺はこうした斑点の一つに、小さな星を見つけて、じっとそれを見つめだした。「今晩だ」と、その星はささやいた。「今晩だ」、と俺は決心した。
そのときなんだ。ふいにあの女の子が俺のひじをつかまえたのは。
通りはもうがらんとして人っ子一人いなかった。だいぶ離れたところで、辻待ち馬車の御者が馬車のうえで居眠りをしていた。
コロス(女):八つぐらいの女の子。頭を布で包んで、着ているものは一枚きり、しかも体じゅうぐっしょり濡れていた。
おかしな男:俺はとくに濡れたぼろ靴が目についた。今でも覚えている。なんだか特別ちらっと俺の目に映ったのだ。
女の子はいきなり俺のひじを引っ張って、呼び始めた。彼女は泣きもしないで、妙に引きちぎった調子で、何か得たいの知れぬ言葉を吐き出すんだ。それもはっきり発音できないのさ。悪寒におそわれ、小刻みに全身をふるわしていたからだ。
コロス(女):「おっ母ちゃん!おっ母ちゃん!」と女の子は叫んでいた。その声には、一種の響きが、ひどくおびえた子供に絶望のしるしとしてあらわれるあの響きがあった。
おかしな男:俺はその響きを知っている。母親はどこかで死にかかっているにちがいない。誰かの助けを求めてるんだ。きっと。
俺は、しかし、一言もものをいわず、そのまますたすたと歩みを続けた。女の子は駆け出して、おれのひじを引っ張った。俺ははじめ彼女に巡査をさがしだすようにいった。けれど、彼女は突然、小さな両手を合わせてしゃくりあげたり、息をつまらせたりしながら、たえず俺の横について走り続けちっとも離れようとしない。
コロス(女):「おっ母ちゃん!おっ母ちゃん!」と女の子は叫んでいた。その声には、ひどくおびえた子供に絶望のしるしとしてあらわれるあの響きがあった。
おかしな男:そこで俺は、威嚇するように足踏みして、どなりつけてやった。女の子はただ「旦那、旦那……」と叫んだばかりで、急に俺を棄てて、一目散に通りを横切って駆け出した。通りの向こうに誰か見つけたんだろう。助けを求める誰かを。
コロス(男女):おかしな男はアパルトマンの五階の自分の部屋へ上がっていった。彼は自分の机の前のいつもの安楽椅子に、あの深々とした孤独を彼に与えてくれる安楽椅子に腰をおろし、考え始めた。引き出しから素敵なピストルを取り出し、机の上に置き。
(女)おかしな男は考え始めた。なぜなんだろうと?
おかしな男:俺はきっと間違いなくあの子供を助けてやるところだった。今でも覚えている。あれはまったくかわいそうでたまらなかった。なにかしら不思議な痛みを感じるほどだった。俺の立場としては、今晩自殺しようと決心した俺の立場としては、実際、あるまじきことと思われるほどだった。
コロス(男):なぜ急におかしな男は無関心でなくなって、あの女の子をかわいそうに思ったのだ? 二時間後に自殺するはずのおかしな男は、いっさいに無関心になったはずのこの男は、なぜかわいそうに思ったのだ?
おかしな男:俺はあの女の子をどなりつけ、追っ払った。二時間たてば、俺は自殺している。いっさいが消滅してしまうのだ。生活も世界も、いわば俺次が第でどうにでもなるのだということが、はっきり頭に浮かんできた。それどころか、いまでは世界は俺一人のために造られたものだ、とさえいうことができる。俺がドンと一発やったら世界もなくなってしまうのだ。少なくとも俺にとっては。実際そうじゃないか! 俺が死んじまえば、誰がどうのってこと自体が消えちまう。つまり、いっさいが誰のためにも存在しなくなるってことさ! 俺の意識が消えるが早いが、全世界はさながら俺一人の意識の付属物かなんぞのように、幻のごとく消えてなくなってしまうはずなんだ!
コロス(女):おかしな男は本当におかしな男。彼は考え込んだ。なぜなんだと。いっさいがどうでもよくなっているはずの自分なのに、なぜ自分はあの女の子がかわいそうでたまらないと感じたのか? なぜ急に無関心でなくなってしまったのか? と。その「なぜ」に、おかしな男は夢中になった。その「なぜ」が解けなければ、もう死ぬことさえできないような気がするほどに。
おかしな男:一口にいえば、あの女の子が俺を助けたのだ。なぜって、俺はさまざまな疑問で引き金をおろす瞬間を延ばしたからだ。そして俺は眠り込んじまった。決心は眠り込んでしまった。そして夢を見た。不思議な夢を。人類の黄金時代の夢を。鹿は獅子のそばに幸せな寝息をたて、万物と万人は互いに愛で結ばれ、そこには永遠の調和があった。その調和の輪さえ掴めれば、殺されるものの苦悶と殺すものの苦悶と、その両方の苦しみの謎が解き明かされるのだ! その永遠の調和の輪が黄金の海のさざなみとなってきらめいていた。次の日、俺は目覚め、ピストルを棄て、伝道の旅に旅立った。謎が解けたことを伝えるための。そうしていまもこのように旅を続けている。
Ⅲ
イワン:おまえは子供が好きかい? アリョーシャ?
わかっている、好きなのさ。おまえは。だからいまぼくがどういうわけで子供のことばかり話そうとするか、おまえにはちゃんと察しがつくだろう。で、もし子供までが同じように地上で恐ろしい苦しみを受けるとすれば、それは、もちろん、自分の父親の身代わりだ。知恵の実を食べた父親の代わりに罰せられるのだ。
だが、これはあの世の人の考え方であって、この地上に住む人間の心には不可解だ。罪なき者が他人の代わりに苦しむなんて法があるもんか! ことに、その罪なき者が子供であってみれば、なおさらのことだ!
こう言えば、驚くかもしれないが、アリョーシャ、ぼくもやっぱり子供が好きなのさ!
コロス(男女):アリョーシャのすぐ上の兄イワンはたくさんのおぞましい虐待された子供の話をした。イワンは毎日の新聞から子供の虐待の記事だけを切り抜き、膨大な資料を蓄えたという。イワンは何度も何度もくりかえした。子供をいじめることには人間の秘密の情欲が隠されているということを。そこにはとてつもない暗い快楽が潜んでいることを。だから人間は子供をいじめつづけているということを。
(女):イワンは神を憎んでいる。イワンは神を許さない。それでもイワンは言う。いつの日か神の国が開かれて、「鹿が獅子のそばに寝ているところや、殺されたものがむくむくと起きあがって、自分を殺した者と抱き合うところを、自分の目で見届けたい、自分のその場に居合わせたい」と。
(男):イワンは言った。「地上におけるすべての宗教はこの希望の上に建てられているのだ」と。そしてこうも言った。「ぼくは信仰する」と。
イワン:ところで、また例の子供だ。いったいわれわれはそんな場合、子供をどうしまつしたらいいだろう?これがぼくの解決できない問題だ。うるさいようだが、もう一度、くりかえして言う。いいかい、すべての人間が苦しまねばならないのは、苦痛をもって永久の調和をあがなうためだとしても、なんのために子供がそこへ引き合いに出されるのだ!
アリョーシャ! お願いだから聞かしてくれないか? なんのために子供までが苦しまなけりゃならないのか、どういうわけで子供までが苦痛をもって調和をあがなわなけりゃならないのか? さっぱりわからないじゃないか! どういうわけで、子供までもが材料の中へはいって、どこの馬の骨だかわからないやつのために、未来の調和の肥やしにならなけりゃならないのだろう!
人間同士の間における罪悪の連帯関係は、ぼくも認める。しかし、子供との間に連帯関係があるとは思えない。もし子供も父のあらゆる悪行にたいして、父と連帯の関係があるというのが真実なら、この真理はあの世に、つまり神の世界に属するもので、ぼくなんかにはわからない。中にはひょうきんなやつがいて、どっちにしたって、子供もそのうちに大きくなるから、まもなくいろんな悪いことをするさ、などと言うかもしれない。
だが、じっさいのところ、その子供はまだ大きくなっていないじゃないか。まだ八つやそこいらのものを、犬で駆り立ててかみ殺させたりして。
おおアリョーシャ! ぼくは決して神を誹謗するわけじゃないよ!
もし天上・地下のものがことごとく一つの賛美の声となって、すべて生あるものと、かつて生ありしものとが声をあわして、「主よ、なんじの言葉は正しかりき。なんとなれば、なんじの道はひらけたればなり!」と叫んだとき、全宇宙がどんなにふるえおののくかということも、ぼくにはよく想像できる。また母親が自分の息子を犬に引き裂かした暴君と抱き合って、三人のものが涙ながらに声をそろえて、「主よ、なんじの言葉は正しかりき!」と叫ぶときには、それこそもちろん、認識の勝利のときが到来したので、いっさいの事物はことごとくその理由と原因が明らかになるのだ。
…………
ところが、またそこへ、コンマがはいる。ねぇ、アリョーシャ!
ぼくはそのとき「主よ」と叫びたくないよ。ぼくは急いで自分を防衛する。神聖なる調和は平にご辞退申し上げる。
なぜって? そんな調和はね、あの臭い牢屋の中で小さなこぶしを固め、われとわが胸を叩きながら、あがなわれることのない涙を流して、「神ちゃま」と祈った哀れな女の子の、一滴の涙にすら値しないからさ!
なぜ値しないか? それはこの涙が永久に、あがなわれることなくして棄てられたからだ。でなければ、調和などというものがあるはずはない。しかし、なんで、何をもってそれをあがなうというのだ? それはそもそもできることだろうか? それとも、暴虐者に復讐をしてあがなうべきだろうか? しかし、われわれに復讐なぞ必要はない。暴虐者のための地獄なぞ必要はない。すでに罪なき者が苦しめられてしまったあとで、地獄なぞがなんの助けになるものか!
いったいこの世界に、許すという権利を持った人がいるだろうか? ぼくは調和なぞはほしくない。つまり、人類にたいする愛のためにほしくないと言うのだ。ぼくはむしろあがなわれざる苦悶をもって終始したい。
…………
ねぇ、アリョーシャ。ぼくは神さまを承認しないのじゃない。ただ「調和」の入場券をつつしんでお返しするだけだ。
Ⅳ
コロス(女):イリューシャは自分で自分の病気を重くして死んでしまった。イリューシャは自分が許せなかった。イリューシャは邪悪なスメルジャコフにそそのかされて、犬のジューチカにピン入りのパンを投げ与え、ジューチカはそれを食べて苦しんだ。苦しんだ果てに死んでしまったかもしれない。イリューシャはコーリャに泣きながら抱きついて、「駆けながら泣いてるんだ、駆けながら泣いてるんだ」とばかり言っていたという。
(男):イリューシャは年上のコーリャが大好きだった。コーリャはずっと年上の子で、強かったし、とても子供とは思えない考えと強い意志をもっていた。クラスの誰もコーリャには逆らえなかった。イリューシャはコーリャに心服していた。コーリャはイリューシャを守ってくれたし、なにか大きな考えの持ち主だったからだ。
イリューシャの父は「へちま」と呼ばれてクラスじゅうの子供たちから馬鹿にされていた。イリューシャの父は世間から道化のように扱われていた。じっさい道化のように振舞っていた。アリョーシャはいつかコーリャにイリューシャの父についてこう言った。「世の中には深い感受性をもちながらも、ひどく押さえつけられているような人があるものです。そういう人の道化じみた行為は、他人にたいする憎悪に満ちた一種の皮肉なんです。長いことしいたげられた結果、臆病になってしまって、人の前では面と向かってほんとうのことが言えないのです」と。
(女):イリューシャは父のことがいちばんわかっていた。父を守っていた。クラスの子供たちはいつもイリューシャをいじめていた。いつもみじめな格好していたから。なによりもあの道化の「へちま」の子供だったからだ。言葉に出してクラスじゅうの子供が父をばかにしたとき、イリューシャはクラスじゅうを敵にまわしても父の名誉を守ろうとした。喧嘩を挑んだイリューシャはクラスじゅうの子供から石を浴びせられた。イリューシャはぼろ雑巾のようになって倒れた。
(男):コーリャはそんなイリューシャを愛していた。クラスの誰もコーリャだけには逆らえなかった。コーリャはいつもイリューシャを守っていた。
(女):イリューシャがスメルジャコフにそそのかされて犬のジューチカにピン入りのパンを食わせたとき、コーリャはイリューシャをひどく軽蔑した素振りをした。おまえとは絶交だと言った。本当は愛していたのだ。少しイリューシャにお灸をすえた後、許してやるつもりだった。
(男):イリューシャはコーリャに心服していた。イリューシャはコーリャだけには軽蔑されたくなかった。でも、イリューシャは軽蔑に値することをしてしまった。
(女):「駆けながら泣いてるんだ、駆けながら泣いてるんだ」とイリューシャは泣いた。自分を許せなかった。そしてコーリャを失ったと思い込んだ。まるで恋人を失ったようにイリューシャは絶望した。イリューシャは父にこう言ったという。「お父さん、ぼくが病気になったのはね、あのときジューチカを殺したからだよ、それで神さまはぼくに罰をお当てになったんだよ」と。
(男):イリューシャがぼろ雑巾のようになって石つぶての嵐のなかに倒れたのはその後のことだ。
アリョーシャ:みなさん、わたしはここで、……この場で、みなさんにちょっと言っておきたいことがあります!
もしかしたら、わたしたちは悪人になるかもしれません。悪行をさけることができないかもしれません。人間の涙を笑うようになるかもしれません。さっき、コーリャ君が「すべての人のために苦しみたい」、と叫ばれましたが、そういう人に向かって、毒々しい嘲笑を浴びせかけるようになるかもしれません。もしわたしたちがそういう悪人になったとしても、こうしてイリューシャを葬ったことや、死ぬまえの幾日かのあいだ彼を愛したことや、今この石のそばでお互いに親しく語り合ったことを思い出したら、もしかりにわたしたちが残酷で皮肉な人間になったとしても、今のこの瞬間にわたしたちが善良な人間であったということを、内心嘲笑するような勇気はないでしょう!
それどころか、この一つの追憶がわたしたちを大なる悪からまもってくれるでしょう。
何でも楽しい日の思い出ほど、ことに子供の時分、親のひざもとで暮らした日の思い出ほど、その後の一生涯にとって尊く力強い、健全で有益なものはありません。過去にそういう追憶をたくさんあつめたものは、一生救われるのです。もしそういうものが一つでも、わたしたちの心に残っておれば、その思い出はいつかわたしたちを救うでしょう。
コロス:ねぇ、アリョーシャ
ねぇ、アリョーシャ
ねぇ、アリョーシャ
…………(一人一人、さまざまな声と調子で)
(了)
あとがき
ドストエフスキーは後期の五大長編(『罪と罰』・『白痴』・『悪霊』・『カラマーゾフの兄弟』)の執筆と並行して、『作家の日記』と題する個人誌を発行し、実に旺盛な評論活動――政治評論、さまざまな犯罪や裁判に関する社会評論、作家論や作品論、回想等のすべてをカバーする――をおこなったが、そのなかに、幼少期の思い出が人間にとって実は一生を支配し、方向付けるような重大な意義をもつことを力説する次のような文章が遺されている。それは内容的に右の脚本のなかのアリョーシャの言葉(それは『カラマーゾフの兄弟』から採ったものだが)にほとんど重なるものである。一言でいうなら、これは彼の根本的な人生観といえるものだから、彼の全作品はこの観点の上に構築されたのだといっても決して過言ではないのだ。引用しよう。
「現代の子供たちもいずれは神聖な思い出を持つようになるに相違ない。〔略〕それでなければ生きた生活は中断されてしまうからである。子供の時分の思い出からその人生に繰り入れられた神聖で貴重なものがなければ、人間は生きていくことすらもできない。〔略〕こうした思い出はあるいはどうにもやりきれない、苦いと言ってもいいものであるかもしれないが、しかし苦しみも過去のものとなればやがてはその人の魂にとって聖なるものに変わりうるものなのだ。人間は大体において、その過去の苦しみを愛するように創られているものなのである。そればかりでなく、人間はもともと必然的に、その過去の要所要所に点を打ち、それによって将来の目標を定め、習慣的にそしてまた自分の教訓のために、それを土台にしてせめてなにかまとまったものを引きだそうとする傾向をもっている。そのさい、最も強烈で最も影響力の大きな思い出は、ほとんどつねに子供の時分の思い出と相場が決まっている。したがって、思い出や印象、それもおそらく、この上なく強烈で神聖な思い出や印象が現代の子供たちによって人生に繰り入れられることになるのは、疑う余地もない」[1]。
だから、本書『いのちを旅する』というタイトルの言葉をそのまま用いるなら、僕たちは自分の「いのち」にしろ、他人のそれにしろ、その「いのち」の最も奥深い《声》にあらためて触れようとするなら、あるいはそれに向き合いたいと思うならば、その「いのち」をその「幼少期」にまでさかのぼる旅を試みなければならないのだ。いろいろな言い方ができるであろうが、「いのち」とは本質的に「旅」なのだ。聖なる幼少期の或る記憶や印象に促され、無意識のうちに僕たちは人生という旅に旅立ち、またその旅の途中で、自分の歩行の姿勢とその方角をあらためて確かなものにしようと、時にその記憶や印象に出会いなおす旅に出る。往きて還る往還の旅を何度もくりかえしながら、「いのちを旅する」ことが、すなわち「いのちである」ということなのだ。
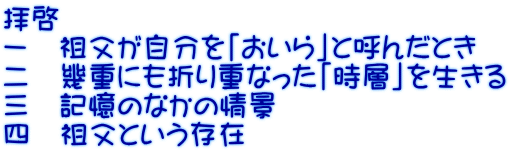
一 今日、ふと気づいた
今日、ふと気づいた。
人生のうちには、おそらくたった一回だけれども、親が子供のもっともよき友達でありうる時期というものがあることに。
去年のことだが、ある一時期ぼくは末の娘の鮎子と絵本をつくる遊びに楽しい時を過ごした。
鮎子はぼくの横に立ち、ぼくはワープロを机の上に置く。そして、彼女が空想の物語を語り出す。ぼくは口述筆記者の役回りだ。
それは、彼女があらかじめ思案を重ね練りあげた一つの物語をおもむろに語り出すというのではもちろんない。そんなことはまだ七歳の鮎子には不可能だし、またそれでは遊びにならない。ぼくたちがおこなうのは〈物語ること〉を遊ぶ、このことだ。この遊びでは、なににもまして物語は口から出まかせでなければならない。思いつきから出発し、その思いつきが連想を呼び、それがまた連想を呼ぶというようにして、あくまで遊びのなかで生まれてくるのでなければならない。
彼女は三匹の主人公をまず思いついた。ぞうのジュニーとうさぎのアニー、それにりすのファニー。彼女は以前ビデオで『アニー』という、十歳ぐらいの孤児の女の子が主人公のアメリカのミュージカル映画を見たことがあった。それは彼女のお気に入りのビデオとなった。主人公たちに名前が必要となったとき、たぶん彼女の頭のなかにふとアニー都いう名前が浮かび、その音の響きがジュニーとファニーという二つの名前を思いつかせたにちがいない。思いつきとはたいてい突拍子もないものだ。他人には理解しがたい距離をそれは楽々と越えてしまう。物語はこんなふうに始まった。
あるところに、どうぶつえんがありました。
その名前は、
『ぞうけんきゅうどうぶつえん』でした。
そこには、
いろいろなぞうがいました。
サルぞうは五とうもいました。
あるひ、そのこまったことがいっぱいあったので、
しいくがかりの人は、
よる、カギをしめるのをわすれてしまいました。
そして鮎子はこう続けた。
サルぞうの一とうだけが、
みんなとなかよくできないので、
しいくがかりの人はこまつていました。
あるひ、
そのこまつたことがいっぱいあったので、
しいくがかりの人は、
よる
カギをしめるのをわすれてしまいました。
そのまに、
ぞうはにげてしまいました。
ぞうのほんとうの名前は、
ジユニーです。
彼女の口をついて出てくる物語をぼくは何度も訊き直しながら、一行一行ワープロに打ち込んでゆく。彼女はそのたびに物語を反錫し、ときどき言い方を少し変えたり、新しく生まれたアイデアに物語の筋をまるっきり変更したりする。
ぼくは聞きながらひそかに考える。
サルぞうなんて象はいたかな。猿みたいな顔の象なんだろうな。「サルぞうの一とうだけが、みんなとなかよくできないので、しいくがかりの人はこまっていました」だって、なるほどなるほど、それがなによりもまず小学一年生の鮎子にとっての〈問題〉つてわけだ。ある問題状況が与えられ、その解決を求めて人は行動に出る。いくつかの選択肢があり、人間はそのうちの一つを選ぶ。状況のなかに頭を抱えてうずくまっている選択肢もあれば、その外に思い切って打って出ようとする選択肢もある。つまり、冒険を呼び起こすことになる選択肢もあるわけだ。その選択が次にその人間をどんな困難に出会わせるのか、そしてどんな人間が助けにやってきたり、友達になったりするのか、人間は自分の冒険の未来をどんなふうに想像することができるのか、小学一年生の鮎子はそれをどう物語るのか。そのとき、彼女は自分自身のどんな〈経験〉を元手にして想像をくりひろげるのか。これまでにテレビや漫画や絵本のなかで彼女が出会ったさまざまな物語やヒーローたちが、今度は彼女自身の物語のなかに少し姿を変えながらどんなふうに引用されるのか。どんなふうにこの三匹の動物たちが鮎子の分身となるのか。それを考える楽しみがぼくの側に生まれる。
「あるひ、そのこまつたことがいっぱいあったので、しいくがかりの人は、
よる、カギをしめるのをわすれてしまいました。」
人間という存在の不思議さがぼくの胸のなかにやってくる。彼女はまだ七歳、つまりまだ七年間しか人生を生きていないわけだが、もうずっと以前からこの世に存在しているように思える。困ったことがいっぱいあったので自分の大切な仕事を忘れてしまうほどの、そんな困った経験をもうしているのだから、彼女はとっくに一人前の人間というわけなのだ。
らちもなくそんなことを頭の片隅で考えながら、ぼくは訊き直し、訊き直し、彼女の思いつく物語をワープロに打ち込んでゆく。彼女はぼくがワープロに打ち込むまでの時間を待たなければならないし、ぼくは彼女のなかに次のアイデアが浮かぶまでの時間を待たなければならない。そんなふうにゆっくり、ゆっくり、物語はお互いのリズムを尊重しながら進む。小一時間も遊んだら、二人とも疲れて、あきてしまう。すると、その日の物語はおしまいとなる。
ぼくはワープロに打ち込んだ物語を印刷し、それを一頁に数行ずつ、大きな余白を残しながら、スケッチブックに切り貼りする。あとでそこに挿絵を描くためにである。その日の夕食後だとか、次の日だとか、あるいはこの次の日曜日だとかに。ぼくは口述筆記者であり、同時に挿絵画家なのだ。彼女は物語を提案し、ぼくは挿絵を提案する。二人で絵本をつくるという遊びをぼくは思いつき、鮎子と実際に試みてみたのだ。
二 親が子供の親友である時期がある
三 〈世界〉遊びを遊ぶ
四 ぼくは記憶のなかに探しにゆく
五 「あまやどりの木」の経験を記憶のなかに
六 〈経験〉はもういちど自分を誕生させる
ナポリ‐アテネ放浪記
(このホームページの、僕の写真ギャラリー「記憶瞬間」に収録されている
「僕の路上絵商売」はこの放浪旅行の時の写真です。マルコも写っています。)
一 ボローニャのマルコ
描いてきた絵を自家製ポストカードにしたものや、女のヌードや大道ミュージシャンたちのクロッキーを描きためたもの、それらを路上で売って日々の宿代と食費を稼ぎ、異国を旅する。このアイデアが浮かび、最初に実行に移したのは二〇〇四年夏のボローニャ。
僕はそこでマルコに出会った。
聖ステファノ教会横の回廊に僕はビニールシート一枚の店を開いた。客寄せに日本から携えてきた油彩数点を回廊の大きな大理石の柱を囲むように並べ、シートの上にポストカードとクロッキーを広げ、道行く人々に「ヴェデーレ・ペルファボーレ(見よ・どうぞ)」と呼びかける。すると、そこにマルコがやってきた。彼はこの回廊に住む野宿者、僕のお隣さんだったのだ。気がつけば、僕が広げた店の十メートル先に彼は住んでいた。赤いボロ自転車の上にはちきれそうな紙袋やビニール袋を満載し、その袋の折り重なりは自転車の立てかけてある回廊の内陣の低い側壁の上にも続いていた。側壁は彼のベッドでもあった。それで全部だった、彼の住まいは。
マルコは、たどたどしく、しかしはっきりした日本語で、「ありがとうございます」と僕の「ペルファボーレ」に応じた。「まるこ、マルコ、丸古」と紙の切れ端に日本の字で書いて、自分を指さし「マルコ」といった。いろんな日本語の単語を口にしては自慢した。彼はそれをフィレンツェの日本人から習った。しかも、彼は英語も話せた。互いに片言の英語で、しかし、僕たちはかなりのことを話し合った。僕は三日この回廊に通って店を張った。僕たちは三日語り合った。語り合う僕たちの五メートル手前の回廊にはアコーディオン弾きがいた。帽子が彼の前には投げ銭入れとして置かれていた。回廊にはいつも有名なシャンソンやイタリア映画の主題歌を奏でる彼のアコーディオンの音色が流れていた。
この回廊にマルコはもう十ヶ月住んでいる。以前はフィレンツェでホームレスをしていた。トスカナの田舎出で、家が貧しく中学には時々しかいけなかった。犬より猫が好きだという。なぜなら、猫の方が自由だから。犬は主人をもっている。猫にはいない、と。工場に何度も勤めたが、どれも長くは続かなかった。気がつくとホームレスの生活に入っていた。
彼の発明品を見せてくれる。底のちょっと上に小さな穴が数カ所開けてあるペットボトル。それから水を滴らせて、手と足とペニスの先を洗うために彼が工夫したもの。ボローニャには体を洗うのに利用できる外についた水道や噴水はないという。噴水に手を差し出すと自動的にストップするのだという。このペットボトルからだとほんの少量の水で要に足りると自慢した。足を洗うとリフレッシュすると強調する。木の花からとった蜂蜜やアロマエキス、ビール酵母など、彼独特の自然食品で自分の健康を守っていた。
彼は自分を蔑む視線につねに苛立ち怒っている。彼は女が嫌いだ。なぜなら、女はあからさまに彼を恐怖するから。一種のしなだ。汚く怖いものを見たというしなをつくって、自分は繊細で清潔な可愛い女だと誇示するというわけだ。かまととだ。独白に近いマルコの怒りの言葉がえんえんと続く。話しているうちに彼は聞き手の存在を忘れてしまう。言葉が言葉を生み、彼の言葉は独白へとかわる。道行く人間たちを「フェット、フェット、フェット(デブ、デブ、デブ)」と小声で罵倒する。こんなこともいった。あるとき、従兄弟の同じ名のマルコがこういった。「なあマルコ、人々はたった三つのことしか考えてないぜ。セックス、金、権力。すべては自分のものという考えで良い心を失ってしまった。人を尊敬することを忘れてしまった」、と。「だから、イタリア人はみんなデブになった」と彼は回廊を行く人間たちを横目に僕に囁く。秘密を囁くように。
マルコは山をなす紙袋に拾ったあらゆるものを詰め込んでいた。ヤドカリのようにその紙袋を自転車に満載し、紙袋とともに彼は移動するにちがいない。無一物であることの不安は彼にあらゆる拾い物を集めさせる。紙袋の山ができるのは、捨てることかできないからだ。拾うということは、拾うことしかできない人間には恐ろしいほどの幸運である。何か役立つときがくるという信念がマルコの所有するけちな拾い物にはこびりついている。取り逃がした幸運は二度と戻ってこないという信念が。古新聞だけで一包みあった。それは、彼が家財道具の類を小さな折りたたみキャンピングナイフと赤いボロ自転車以外にほとんど持ちあわせないからだ。
拾い物といえば、路上の商売にとって客はまさに拾い物である。
店がそこにできれば人はそこを確立した一つの秩序として知る。そこに行けば必ずその店があり、その店には必ずその商品が置かれてあり、価格は既に定められている。そこには三重の安定が、約束が、当てにできる予想がある。
だが、路上商売にはまさにそれがない。明日はその店はない。既にその商品は売れてしまった。価格は昨日よりも高いか、あるいはもっとずっと安いかだ。僕は客がつかないと感じるや、その日のうちにディスカウントした。売れると見るや、買った客が立ち去るや、値上げした。明日は雨かもしれない。警官がやってきて追っ払われるかもしれない。路上商売はお日様と運と共にある。明日はないものと知れ!それが路上商売の鉄則だ。あるいは路上生活の。僕にとっても、客にとっても。さあ、さあ、今しかないよ!お客さん!明日はないんだぜ、お客さん!
旅の出会いもこの種の拾い物だ。今日を限りの出会いなんだから。三日たってマルコに別れを告げるとき、また来年お前はここにいるだろうかと聞く。彼は答えた。明日のことはわからない。今は夏、だから俺はここに住んでいるが、長い冬をどこで暮らすかはわからない。冬が終わって俺が元気かどうかも、と。もちろん僕にもわかっていた。二度と彼に僕が会うことはないことは。僕は遠い異国の二度と来ないであろう街の一角に立っているのだから。遠い旅の路上で出会ったのだから。旅は人生を凝縮してしめす。ふだんの暮らしのなかで、僕たちは昨日も今日も明日もその人間と会えると思っている。いや、実際会えるにちがいない。たいていの場合は。だが、そのときの彼、そのときの彼女とはそのときにしか出会えない。二度と。ときとして、そのことは大きな意味をもつ。
彼は小学校しか出ていない。だが、素晴らしい教養をもっていて、イタリアの歴史をあれこれ説明してくれる。またこんなことも。リラがユーロに変わってから、いかに物価が値上がり、同時にまたいかにホームレスたちが都市の目に見える景観のなかから追い払われたかを。日本と同様、ヨーロッパをあの勝ち組・負け組み=市場原理主義の新自由主義が席巻している。そう、マルコのいうとおり、イタリア人はみんな「デブ」になった。ヨーロッパ社会の下から三分の一の階層はいまや完璧に移民労働者だ。貧しき者の鬱屈と切ない愛とたくまざるユーモアにお祭り騒ぎ、庶民の臭いに満ち満ちたあの昔のイタリア映画の主人公たちはいまやミドルクラスだ。往年の主人公たちを現在のイタリアで引き受けているのは移民たちだ。まず隣国の旧ユーゴを筆頭に東欧バルカン諸国の人間たちとアフリカの旧植民地からの黒人たち、ロシア人、アラブ人、パキスタン人、インド人、それに中国人、あらゆる国からやってきている移民労働者たち。ボローニャの小さな中華料理屋ではいつも黒人が食事していた。安いからだ。マルコはイタリア人から転落したイタリア人。
彼は映画が好きで、いろんな監督の名が話のなかに出てくる。でも一番はフェリーニ。会った最初の日に、フェリーニのつくった『アマルコルド』の話が飛び出した。僕にとっては青春の思い出と結びつく映画で、フェリーニのなかでも僕の好きな三本の指に入る作品だ。だからそのとたん僕とマルコは友達になった。「ストラーダ」というイタリア語が「道」という意味の言葉だと知ったのもこのときだ。「お前のベストワンは?」と聞くと、「ストラーダ」と答えた。僕が「何?」という顔つきをすると、すかさず「way」と答えた。フェリーニのあの『道』!ジュリエッタ・マシーナとアンソニー・クインのあの『道』!
戦後イタリアの最高のコメディアンの話もしてくれた。だが、そのとき僕はその名を覚えることができなかった。マルコによれば、三十年たっても、人々は覚えていて、彼を超えるものはまだないという。(だが、僕は今度のナポリの旅で思い出した。「トトー」というのだ。スパッカ・ナポリ地区の露店でコメディアンの古い写真を売っていて、それは誰だと僕が聞くと、露天商のオヤジは「トトー」だといった。マルコは、そのコメディアンはナポリタンだといっていた。そのことを思い出した。オヤジは、トトーはナポリタンだと胸を張って答えた。)
僕はこのボローニャの旅から帰って、十二枚の詩画集風の絵とそれに添える詩を作って或る絵本のコンペに応募した。そのとき、僕はマルコとの出会いを次のような詩につくった。
マルコ
フェリーニ!
アマルコルド!
リコルダル ミ! Remember!
《知っているよ マルコ!》
『私は思い出す』
海沿いの村の空
季節はずれの灰青色の貴婦人
たった一羽
飛んでくる
誰かが見つけて 叫んだ
《誰が?》
村に一軒の居酒屋、村に一軒の床屋、村に一軒の葬儀屋、
村に一人の駐在、村に一人の神父、村に一人の教師、
村に一人の詐欺師
そんな誰か
《ああ そこでは誰もが 村に一人の誰かなんだよ!》
ほら、子どもが飛行船を見つけたときのようにだよ
あそこ!
村中の人間が
情事に励んでいた二人も
窓をあけて
阿呆の口をあけて
真底美しいものを見た口になって
アマルコルド!
《リコルダル ミ!》
夏のボローニャ の
マルコ
聖ステファン教会横の回廊に
自転車一台にいくつもの袋をぶらさげ
一人住んでいる
ミオ アミーゴ! my friend
クェルケ ヴォルタ ドーヴェ リコルダル ミ
ケ ドーヴェ リコルダーレ
(時に私は思い出さねばならぬ
思い出すべきことを)
君の
教えてくれたイタリアの言葉
二 ナポリでの路上商売
マルコとの出会いがあって、一年半がたち、僕はそのあいだ病が再発し仕事も休まねばならなかったのだが、回復するや、すぐ第二の旅に立った。絵を売って異国を旅する試みを再開したのだ。
以下、今度はそのときつけた旅日記からいくつかのページを拾い出し、それをそのまま開くような形で語ってみよう。気分を変えるために「僕」という主語を「俺」に変えてみたい。すると、まるでそこには青年の自分がいるようではないか。
* *
十二月二三日 早朝ローマに着く。すぐナポリ行きの列車に飛び乗って昼前には着き、ユースホテルに荷物を降ろすや、中心のダンテ広場に絵を売りにいくつもりだった。いかに俺はこの旅で「絵を売って旅する」という自己イメージに夢中になっていたか。意気込んでいたことか。
だが、着いたときは一時半をまわっていた。イタリア語を少しは事前に覚えてゆく計画は結局放棄。俺の旅はつねに泥縄式。旅の開始日に押っ取り刀で駆けつける。言葉がほとんど通じず、しかも、初めて訪れる街での行動は、机上で立てた予定時間の二倍はかかる。これまでの経験から十分わかっていたはずだ。その日に絵を売りに出かける計画は捨てた。下見をかねてナポリのメインストリートを歩く。歩きとおす。
ナポリ観光を支える交通の中心になるのはR2のバス。その始発ステーションを探す。見つけられない。それがあるはずのナポリ中央駅前のガリバルデイ広場は、俺の先入見をはるかに越えて広かった。理由はそれだけじゃない。余りにも乱雑に車がひっきりなしに乗り入れ、しかも工事中の場所がいくつもあって、広場という観念を俺の頭から叩き落したからだ。整然と樹木なり由緒ある建物によって取り囲まれ、くっきりと周りから区切られ、台座の上には騎馬に乗った王か将軍がいて、孤独に周りを睥睨し、人影はむしろまばらで、当然内部には車なぞ立ち入り禁止で、閑散としたその区域の上には四角に区切られた明るいイタリア南部の空が遥かに開かれている。それが「広場」のはず、それでこそ「広場」というものだ。そうじゃないのか?
だが、そんなイメージを吹き飛ばす或る荒廃と無秩序がそこにはあった。後に訪れたアテネから振り返ってみても、ナポリが最初に強烈に俺を打った印象、「ナポリには信号がない」という印象は正確だった。
アテネは、小なりといえどギリシアという国家の首都だ。しかもアクロポリスのパルテノン神殿を戴く世界屈指の国際観光都市。さらについ数年前にオリンピック開催を成し遂げた。街中は新ピカ、清潔、整然。街を行き交う人々の顔は明るく、温和で、落ち着いていた。暗鬱なもの、苛立ち、居直りの哄笑はなかった。交通は指揮されていた。整然たる信号によって。人々は信号を待つ余裕をもつ。全然違う。ナポリは。
ヨーロッパの車はあくまで一個のマシンであり道具に過ぎない。だから埃まみれだ。車を毎日のように洗車し新車の輝きと身綺麗さを保つていないと耐えられないといった、車への美意識はない。その埃まみれの車や二人乗りもざらでないバイクの群れが突っ込んでくる。ナポリでは。ひどいスピードで傍若無人に。細い坂道の石畳の路地の奥の奥にまで、人を蹴散らすように警笛を鳴ら、石畳の上を小刻みにバウンドしながら。
だが、人間もまたどこ吹く風だ。人影を見れば車は必ず止まるかスピードを落とす。人々は何の不安も見せない。突入してくる車の波に頃合を見はらかって巧みに割って入り、手を上げて車を止め、落ち着き払って横切ってゆく。信号がないからといって生きるための約束がないわけではない。いや、それは断乎としてあるんだ。眼に見えないだけだ。俺たちと違ってるだけだ。
ナポリは俺の心を打った。このアナーキーな、しかし、人間臭さに満ちあふれた、小型車とバイクのスピードによって。
実際ナポリは人間臭い。ナポリの下町として有名なスパッカ・ナポリ地区とスペイン地区。人々が行き交う路地には洗濯物が窓からぶら下がっていた。あるいは路地をまたがって向かい合う窓と窓とのあいだに渡されたロープがそれをつるしていた。人型のシャツやセーター、さかさまのズボン、逆向きにひるがえる白旗のようなシーツや色とりどりのカーテン。細く歩きにくい石畳の路地の両脇に立つ三、四階建ての古びた石造りのアパルトマン。そのいくつもの窓から。三階の窓から老婆が紐をつけたバケツを降ろす。夫に違いない。老人が買い物の品をそこにいれて、引っ張り上げあげるよう合図を送る。俺は数日のうちに三回はこうした場面に出会った。二階か三階にいる隣人と路上の或る女が大声をあげてやりとりしている。二回は出会った。喧嘩だったのか、それともちょっとした元気に弾んだ会話だったのか。どっちにしろ、威勢がいい。
ガリバルディ広場駅前は軒並み黒人たちの屋台。駅広場から始まる大通りのボローニャ通りだったかトリノ通りは、歩道ではなく、道の真ん中そのものが埋め尽くされている。黒人たりの屋台で。うさんくさい海賊版のブランド風革製品やアフリカの民芸品、その他雑多なチープな商品。道の奥の奥まで。屋台の黒い河だ!黒い運河だ!俺は口走る。「ここはイタリアの第三世界だ!」。
ろくな産業がない。まともな会社はほんのわずか。失業者に溢れた貧しい大都市では、人間はチープな雑貨をどこからか仕入れてきては、道端で売って、互いに金を回しあい、生き延びる。ナポリの道端商売の驚くほどの数は、ここが今でも貧困の大都市だということの証しだ。
直観する。この貧困の双生児が、あの信号なしのアナーキーな小型車とバイクのスピードだ!。金持ちはもちろん、れっきとした「市民」様ならつねに余裕というものの所有者だ。待っていることができる階層、それが彼ら。礼儀とは時間の余裕。余裕が可能なのは時間に秩序が許されているから。計画を合理的に追求することが可能だから。それが「市民」生活というものを成り立たせる原則であり、前提だ。
だが、貧困を生きる人間には時間の余裕に満ちた合理性なぞない。欲しくても持てない。彼らは失業中だ。あるいは、ありつけた仕事は恐ろしく単調でハードだ。することがなくて時間を持て余してるか、もう何もできないほどくたくたか、二つに一つ。アルコールかヤクによる酩酊か、もし、バイクか小型車があるなら、スピードの快楽に憂さを晴らすか。二つに一つ。彼らは一方ではおそろしくだらしなくルーズで時間の観念は無きに等しい。他方では、いつもひどく早口で、喧嘩ぱやく、短気で、荒々しく話すことが好きで、車やバイクにまたがればスピードに酔いしれる。一種の法則だ。
こういうことの一切はアテネの表通りにはなかった。ナポリにはあった。あったどころじゃない。表通りがそのままこの世界。
十二月二四日 ダンテの像が立つダンテ広場の中央より少し端のベンチの一角。今日の俺の店。ベンチの半分におずおずと客寄せ用にもってきた油絵数点、その前の地面にシート、その上にたくさんのポストカードとスケッチ、詩画集を数冊。ポストカードは一枚一ユーロ、スケッチは二ユーロ、詩画集は一〇ユーロ。
今日はクリスマスイブ。街中は買い物に活気づく。ダンテ広場はナポリ観光のメイン広場。店を張るには躊躇があった。一昨年のボローニャではメインの広場で店を張るや、警官に追っ払われた。同じ路上商売をしている連中から侵入者として排斥される危険、これはない。ヨーロッパには地回りはいない。ボローニャで確信した。だが、警察は別だ。
パトカーが、おずおずと開いた俺のシートの店の目の前に止まる。尻を向けて。広場の警備。だが、何もいわれない。おぉ、なんという幸運!最初に詩画集が一冊売れる。中年の男が面白がって買ってくれる。幸先がいい!俺の右目の端に広場の小さなエスニックな衣料雑貨店が映っている。そのオヤジがやって来る。小柄な髭もじゃ、この商売のオヤジなら当然こうだと感じさせる風体、イタリア人なんだろうか、東欧系ではないのか、ギリシャ人か? タンゴのバンドネオン弾きを描いた俺の油彩の絵を見て、いくらだという。五〇〇ユーロと答える。がっかりした様子。はじめ俺はイタリア語で五〇〇ユーロといった。うろ覚えで発音が曖昧だから、相手は五〇ユーロと思ったらしい。それなら考えてもいいという表情となった。念のため俺がメモ帳に金額を書いて示すと、とてもとてもという顔。
路上商売には路上価格というものがある。ワン・コインの世界。仮に五〇〇ユーロの価値がある商品でも、それを路上で買うバカはいない。価格にはそれにふさわしい場所というものがある。場所が価格の保証だ。もう俺はそれをボローニャで学んだ。今回油彩を持ってきたのはあくまで客寄せ。売れるとは思っていない。
絵を気に入ってくれたことが嬉しい。俺はバンドネオン弾きを描いたスケッチの一枚を、プレゼントだといって奴に渡した。二度目にやってきたとき、奴は広場のカフェからエスプレッソを小皿に載せてもってきた。俺のために。だから旅はこたえられない。いっぺんに友達になる。人間を繋げるのは言葉ではない。行為だ。状況だ。心意気だ。言葉が通じなくなれば直観が冴え渡る。好きか嫌いかは顔を見ればわかる。店の手伝いをしている彼の息子の十八ぐらいの青年がもう一度いくらだと聞きにくる。バンドネオン弾きの絵はオヤジの心も息子の心も捉えた。安ければ買いたい、そこまでは奴らの心を捉えた。俺は満足。
この日俺の商売は三〇ユーロに届いた。やっとだ。問題だ。ナポリのユースの宿代は一泊のドミトリー(六人部屋)が一四ユーロ。ユースがあるメルジェッリーナとダンテ広場に一番近い地下鉄の駅、カブール広場駅とを往復する地下鉄代はすべての公共交通共通券の一日フリーパスで保証する。それは一日三ユーロ。どんなに食事を落としても一〇ユーロはいる。最低二七ユーロ。それをわずかにクリアするだけの金額。
後で俺は「カメレオン化現象」と名づけた。自分を振り返って。俺は、いざとなれば、もってきたクレジットカードでナポリのATMから最低限の旅を全額保証するぐらいの金額は引き出すことができる。万一を考えて、そのぐらいの準備はした。その意識はつねに頭の片隅にある。だが、路上商売を始めるや、その意識はほとんど作動しなくなった。いわゆる演技しているというのともちがう。実際に、そのときは、大道で絵を売ってその日を暮らしながら旅を続ける人間になった、俺は。実際の俺の存在のモードが、またそこから来る気分と思考のモードが、まるでカメレオンが環境に応じて身体の色を変えてしまうように、変わってしまう。事実俺は必死だった。俺は食事の水準を落とした。今日三〇ユーロしか稼げなかった以上、食事はビール一杯の値段も込みで一〇ユーロ以内に抑える。ナポリの普通のピッツアリア(ピッツア屋)でピッツアを一皿注文すると、その大きさは日本のビッグサイズよりもうひとまわり大きい。一人でそれを全部平らげたら満腹以上だ。その一皿が四ユーロから六ユーロ。ビールはイタリア国産のビールの大瓶で二・五か三ユーロ。三〇ユーロ稼げたことは一日暮らせるということだ。
見ていて手作りポストカードが一番売れる。詩画集三〇枚のカードを見本として並べるより、それ以外の種類のものもたくさんまぜて渾然と広げた方が売れる。探す楽しみというものが生まれてくるからだ。「これしかありません」と整然と提示されると、自分で探す楽しみ、思いがけないものを発見する楽しみが損なわれる。路上商売にこの楽しみがなかったら、買う楽しみは半減する。買うのはたんにその商品を買うということではない。買うのは、自分がお気に入りを発見し、広い意味で「得をした」ことを買うことだ。「得をした」という気持が生まれなければ絶対に路上商売は成り立たない。「あらゆる商売がそうではないか? 」、もちろん当然の反論だ。だがこの要素は、路上商売では普通の町場の確立した店商売とは比較を絶してる。それは路上商売の絶対生命。今日、俺はこの教訓を噛み締めた。この旅に持ち込むべき俺の商品はもっと多様であるべきだった。
広場を去るとき、エスプレッソの髭もじゃオヤジに「ドマーニ、チャオ」といいにいく。「明日また」と。奴はにっこり笑う。
ユースに帰って、商売道具を置き、小一時間ベッドに転がって体を休めてから夜のナポリに繰り出す。四時間は歩いた。クリスマスイブのナポリを見たい。今日の徘徊の世界は下町の代表、スパッカ・ナポリ地区。ガリバルディ広場駅まで地下鉄で行き、そこで降りて、最大の通りであるウンベルト大通りを南下し、途中で右側の路地に入り込んで、大体の見当で、クリスマス市が開かれているサン・グレオリオ・アメーノ通りを目指す。その辺りがスパッカ・ナポリの中心。歩きに歩いた。
この夜の散歩が自分のなかに醸し出したモチーフをちょっと創作風に描き出してみよう。アテネを去る最後の夜の日記からちょっとだけ引いて、終わりにしよう。
一月六日 ユースに戻るとベルギー人だというハッサムと名のる男がいる。彼と英語でカタコトのおしゃべりをする。絵を見せてくれという話になる。見せる。彼は特に女のヌードスケッチが気に入って、数枚プレゼントしてくれという。わずか一枚二ユーロのスケッチを、気に入ったから買ってやろうとはいわず、臆面もなくプレゼントしてくれというところが何とも面白い。俺は四、五人女がいて、強いんだという。お前は女を知っていると、スケッチを見ながらいう。女のプロからの何よりの誉め言葉。少し面映い。「of course, I know woman as well as you」といい返すべきだった。
何を仕事にしているのかと聞くと、小さいものから大きいのまであらゆるものを、友人と友人とを繋ぎ、扱っているという。そうそうといって、鞄からフランスの絵筆メーカーの商品カタログのパンフレットを出してきて、お前にやるという。これも俺のビジネスだと。九月一五日以降なら時間ができるから、お前の絵の展示会や販売を考えたい、絵の写真を送ってくれたらカタログをつくって動くからと、住所を交換する。これをプレゼントしてくれといって選び取った数枚のスケッチを鞄からまた出してきて、これを覚えていてくれ、これと同じタイプのスケッチが欲しいという。和紙に墨でぼかした形で女の裸体を描き、その上に黒のボールペンで今度は明確に女の体の線や表情を描きこんだものだ。
ハッサムという名前を見て、初めインド人かイラン人かイラク人かと思ったというと、これはイスラム教徒として一番ポピュラーな名前だという。日本で太郎に当たるような名前なんだろう。祖父の代から自分たちのファミリーはベルギーにいるが、実に多くの国に出かけ、何でも手がけてきたと自慢する。
お前は絵を売っていくら稼いだと聞く。これまでで四五〇ユーロ稼いだと正直に答えて、眠った後で金を狙われる羽目になったらとんでもないと閃いて、ナポリではたった七〇ユーロだ、あそこは貧しいから僕の絵を買う人間があんまりいなかったと答える。すると、彼はベルギーのことをこんな具合に話した。ベルギーには貧しい国から人間がやって来て、もう三世代住んでいる。彼らの国は貧しすぎるから、彼らは絶対にもう自分の国に帰らない。ベルギーにはそういった貧しい人間たちだけが住むエリアができあがっている。それはもう壊すことはできないだろう、と。
ハッサムはTVをつける。かなりの音量で平気で見ている。いかにも真面目そうなドイツ人の青年が、自分は眠りたい、音量が大きいという。するとハッサムは「you criticize me?」とちょっとドスをきかせて問う。すると青年はたじろいで、「No, only I want to sleep」と答え、毛布を頭から被ってベッドに潜り込む。ハッサムはちょっと音量を下げてやるが、それは形だけだ。相変わらず大きな音量でテレビドラマを見ている。中年の夫婦が寝室のダブルベッドで寝物語をしている。その後、夫が隣部屋に出ていって携帯電話で誰かと話す。それは明らかに女が相手で、夫は猫撫で声で相手を口説いているか、言い訳をしている。すると女房がこっそり部屋のドアを開け、その様子を全部見ている。不倫が発覚し、さてこの夫婦はどうなるか、といったありきたりの家庭劇だ。
ハッサムはベルギーに二つの会社を持っているという。九月になったらお前の絵で商売をしてやろうという。しかし、もう五〇代にはなっていると見える彼は、一泊一〇ユーロのアテネのユースのドミトリーの僕の隣のベッドで寝起きしているのだ。アテネでのビジネスのために。僕と同じように。
二人のアジア人の男がアテネのユース・ホステルのドミトリーで自分たちのビジネスの話をし、約束を交わす。共同のビジネスの、嘘か真か、わからぬ約束を。今回の放浪に相応しい終わり方だと僕は一人納得する。
もっとも、僕はハッサムを信用したわけではない。最後の夜にパスポートと航空チケットと現金をユース・ホステルのドミトリーでごっそり盗まれたなんてことになったら、赤恥もいいところだ。僕はしっかりそれらを首から吊るす秘密の袋にまとめ、その袋を抱くように体を九の字に曲げて眠りにつく。